心がザワつく不安感を感じることはありませんか?
その不安解消には、身体を温め、腸を整えると、自然と心も整えいます。
こんにちは。セラピストの鈴木美和です。
新型コロナウイルスの影響で不安な日々が続いています。不安が立て続けに起こると、その不安は余計大きく広がっていきますね。
不安な状況だけではなく、女性は、加齢による外見や体力の変化とともに自分の女性としての魅力がなくなってきたのを感じ始めたころ、
いつも気持ちが暗く憂鬱な感じがしたり
心がザワザワしたり
漠然とした不安を抱えたり
年齢を重ねるごとに不安感も強くなる傾向があります。女性は感情に左右されやすく、様々なバランスが崩れると、生きづらいと思うときもあります。
今回は、漠然とした不安感の原因と解消方法をお伝えします。
不安の原因は女性ホルモンの変化

不安感の原因は、女性ホルモンの変化で、特にエストロゲンの急激な低下があります。このエストロゲンは抗うつを抑えたり、自律神経のバランスを整える作用があります。
そしてもうひとつ、プロゲステロンの低下です。
エストロゲン・プロゲステロンは2大ホルモンで、女性にとって重要なホルモンです。
自律神経も担う脳の視床下部や下垂体との連携で卵巣から分泌するので、ホルモンの減少で自律神経も乱れるため、ここからくるからだの不調も多いのです。
不安に強い脳と体を作る

不安や不調は、長引くとどんどん悪いほうに向いていきます。早く切り替えるコツをつかみ、それらをなくしたいですね。
ここで不安に強い脳とカラダになるヒントをお伝えしていきましょう。
不安に強い脳と体を作る方法
カラダの歪みを治し、血流を良くし体温を上げる
骨盤矯正でカラダのゆがみをなくし、腸を揉みほぐし、血流を良くして体温を上げる。
質の良い睡眠
量より質の良い睡眠が大事です。
副交感神経を優位にすると質の良い睡眠になるので、交感神経を刺激するスマホ等を寝る前に見ない。
食 事
体温を上げる=基礎代謝量を上げる
そのためには食生活も大切です。
筋肉を増やせば基礎代謝は上がりますからタンパク質をしっかりとり、バランスの良い食事をすることが大切です。
「美味しい」「楽しい」と感じることで気持ちが満たされストレスが和らぎます。
ときにはだれかと一緒に心から食事を楽しんでみる。
幸せホルモンが出る栄養素
タンパク質、ビタミン、ミネラル
睡眠と幸せ感に必要な食材
幸せホルモン(セロトニン)と睡眠ホルモン(メラトニン)の合成に必要なトリプトファンは以下の食材に多く含まれています。
- 豆製品…納豆・豆腐・味噌・大豆
- 乳製品…ヨーグルト・チーズ・牛乳
- その他…ナッツ類・バナナ・鶏ひき肉・カツオ・豚レバー
- ナイアシンは、カツオ・マグロ・鶏のむね肉
- ビタミンB₆は、豚ヒレ肉・マグロ・ニンニク
- 鉄は、豚レバー・アサリ・牛肉に多く含まれています。
生活習慣
起きてすぐに朝日を浴びると、約16時間後眠りのホルモンといわれるメラトニンが分泌されて、自然と眠くなります。
そしてよく笑いましょう!
よく笑うことで幸せホルモンのセロトニン分泌につながります。
笑うような心理状態なら、幸せで当たり前と思うかもしれませんが、意識して楽しい映画やテレビを見て笑っている表情を作るだけでも効果があるようです。
多少の不安にも負けない心と身体に!
私のサロンでは、骨盤のゆがみを正し、腸の機能を活発にすることによって血流が良くなり、体温を上げていきます。
腸の調子が良くなれば、さらにからだ全体の調子が上がり、自然と笑顔が増えストレスに強くなっていき、心もハッピーでいることができます。
腸の能力を最大限に引き出せるかどうかは、あなたのちょっとした心がけ次第。
なかなか抜けない不安を抱えている方は、一度試してみてはいかがでしょうか。
人には言えない心の悩みはありますか?多くの方が、悩みを抱えていると思います。
そんな悩みを解放してくれる魔法の小瓶があります。
はじめまして、西丘理桜です。
ハーブやアロマテラピーといった植物の力で心と体を癒す自然療法、植物療法の仕事に携わり20年ほどが経ちました。この20年でアロマもハーブもすっかり私たちの生活になじみ、女性男性、年齢を問わず癒しの手段として楽しまれています。
癒しという事がとても普通の事になって久しいです。
ところが、今も心の中に悩みの種を抱えたまま、一生懸命頑張って日々の時間を過ごしている女性たちが少なくない事を感じます。そんな中、目で見ることのできない「感情」という心の動きをケアする「フラワーレメディ」が、ここへきてじわじわと広がってきています。

私のサロンにおみえになる方は、解決しようと行動に移すことができる方。ほとんどの方は解決したいと思っていても、そのための時間が取れなかったり、自分の弱みを他人に話すのはちょっと抵抗があったり、悩みと向き合うために今一歩の勇気が必要だったりで、結局後回しにして心の奥にしまい込んでいるようです。
心の憂鬱は少しづつ体に影響します。質の良い睡眠がとりづらくなったり、食事のバランスが崩れたり、そうなるとお肌にも影響大。
外側からのケアももちろん大事だけれど、内側からのケアも同時にできれば…いつまでもきれいで輝いているために、フラワーレメディを使って、手軽に心のケアをしてみませんか。
私のサロンではフラワーレメディは、セルフヒーリングという位置づけをしているので、誰かに何かをしてもらう必要がありません。自分に必要なレメディを選んで使う。ただそれだけです。
自分の心の中を覗いて、何が原因で辛いのか?苦しいのか?どうしたら自分が喜べるのか?その目的に合ったレメディを使います。もちろん、お話を聞きながら今必要なレメディを選ぶお手伝いをするのが私の仕事なので、お話いただけるときにはゆっくりじっくり耳を傾けさせていただいています。が、ここでは自分自身で、誰にも知られずに、解決の糸口となるレメディを選ぶ方法をお伝えしていきたいと思います。
まずはレメディを知ることから、スタートです。
フラワーレメディって何?

ハーブは主に表面に出てくる不調を癒してくれます。一方のフラワーレメディは体の奥深くにある心や意識を癒すことを得意とします。
たとえば、怒り・不安・悲しみ・嫉妬のように毎日の生活の中や育ってきた環境の中で知らず知らずに抱えてしまい、日々の生活や人間関係にマイナスに働いてしまう・・・そんなネガティブな感情や意識をていねいにほぐしてケアしていくもの。
100年ほど前にイギリスで始まり、今では世界中でたくさんの種類のレメディが作られ、多くの国や地域でたくさんの人に使われています。
こんな方におすすめ
- 親子関係・夫婦関係・恋愛関係・友人関係等、人間関係が何だかうまくいかない…原因は分かるようで分からない。自分の性格のせいかなあ・・という方。
- ここ一番というところでいつも尻込みしてしまう、自分に自信が持てない方。
- どうせうまくいかなかったはず、と自分を納得させてあきらめてしまうことが多い方。
- 体に不調はないのだけれど、どうもやる気が起きなくて、時間が無為に過ぎていくことを止められない方。
- いつも周りがうらやましくて嫉妬と羨望のドロドロに飲み込まれている方。
- 先のことは考えない、今頑張らなくていつ頑張る?だけど最近ちょっと空回りな気がする方。
- 決められない、あーまた決められない。やっと決めたけれど、もしかしたらあっちの方が良かったのかもしれない・・あーまた決められないという方。
- 自分さえ我慢すればすべて丸く収まるんだからそうしてみたけれど‥あれ?このもやもやは何?という方etc
いかがですか?自分に当てはまるものはありましたか?人はみな多かれ少なかれネガティブな感情を持っています。すべて前向きで100%ポジティブな感情しか持っていない、と豪語される方も時にはいらっしゃいますが、そういう方でさえ、突発的にアクシデントに見舞われるとネガティブな感情に支配されてしまうことが往々にしてあります。

プラスとマイナス上手にバランスを取れれば問題はないのですが、その辺りが中々思うように解決できない方のために、手軽に自分で自分の心と向き合ってコントロールできるフラワーレメディがあり、いつも元気で明るくて前向きに生きるためにひそかに使い始めている女性が増えています。
フラワーレメディの種類
一番最初にフラワーレメディを手掛けたとされているのはイギリスのバッチ博士。その38種類のレメディはパイオニアとして、今も世界中で愛され使われています。
けれども100年前と今では、私たちを取り巻く環境はまるで違います。そのため、当時は38種類あれば人間のマイナス感情をほぼ全てケアする事ができたのですが、今ではより深くより細分化されて、多くの作り手さんが、あらゆる状況に対応できるようたくさんの種類のレメディを世に送り出しています。

はじめはフラワーレメディという名の通り、お花を使ったものが多かったのですが、今ではキノコや海藻など植物はもとより、鉱物や動物など自然界に存在する多くのものを材料にレメディは作られています。
今はネットを通じて世界中から欲しい物を手に入れることができる時代ですが、まずは日本でも手に入れやすくシンプルで分かりやすく、比較的安価なバッチ博士のフラワーレメディを紹介していきたいと思います。
次回から具体的に個々のレメディをとりあげて様々な感情とレメディを対比させながら、解説をしていきたいと思います。お楽しみに。
こんにちは!千葉市でうつ病回復支援専門カウンセラーをしております吉川淳子です。
私は保健師資格もあるので皆さんの心身両面のアドバイスができます。企業での健康管理経験からうつ病で休職・復職した方のサポートも多数させていただいております。
皆さんがメンタル不調にならないためにはストレスを溜めないように自己管理することが大切ですよね。ここでは誰でもできる簡単なストレス解消法をお伝えします。
涙はストレスを流してくれる

嬉しくて泣く、悲しくて泣く、悔しくて泣く、感動して泣く。
実は、『涙』の中にストレス物質が含まれています。泣く事で、ストレス物質が体の外に出ていきます。
感情が動いて出る涙と、玉ねぎを切っている時に出る涙とは、成分が少し異なります。
感情が動いて出る涙には、ストレス物質の副腎皮質ホルモン「コルチゾール」などが流れ出ています。
それだけでなく苦痛を和らげる物質も出てくるので「あー泣いたらスッキリした!」という状態になるのです。
ということは、感情が動いているのに、泣くのを我慢するとストレスが自然に出ていくのを止めてしまうという事になります。状況にもよりますが、出来るだけ涙は流してしまった方が良いですね。
中でもストレス解消効果が高いのは、ポジティブな感情が動いた時の涙と言われています。
ラグビーのトライが決まった瞬間やフィギュアスケートで逆転勝利した瞬間など選手と一緒に流す涙は心身ともにスッキリすること間違いなしです。
なかなか泣けない時はどうする?

ストレス解消したいから涙を流そうと思っても、感情を動かすことが起きなければなかなか難しいことですよね。
ストレスが溜まっているけど、泣けない方は、わざと泣く状況を作ってみるとよいです。
- 泣ける映画を観る
- 泣ける小説を読む
- 泣ける音楽を聴くな
- もしあればご自分が子供の頃に書いた作文や日記、家族写真なども意外と感動します
- 悲しかったこと、悔しかったことなどを、文字にして読んでみる
- 親しい友人などに話しを聞いてもらって泣くのはとても効果的です
ネガティブな感情からの涙はあまり良くないと言う人もいますが、今の感情をタイムリーに涙と言葉で出してしまうのはストレスを溜め込まないためにはやった方が良いのではないかと思います。
泣く場所も考え物ですよね?車の中、お風呂、寝る前の布団の中、海岸、公園など、ひとりになれる場所を見つけてみてください。
私のカウンセリングルームでは思いっきり泣けます!
ちゃんと泣かないと心の病に!?
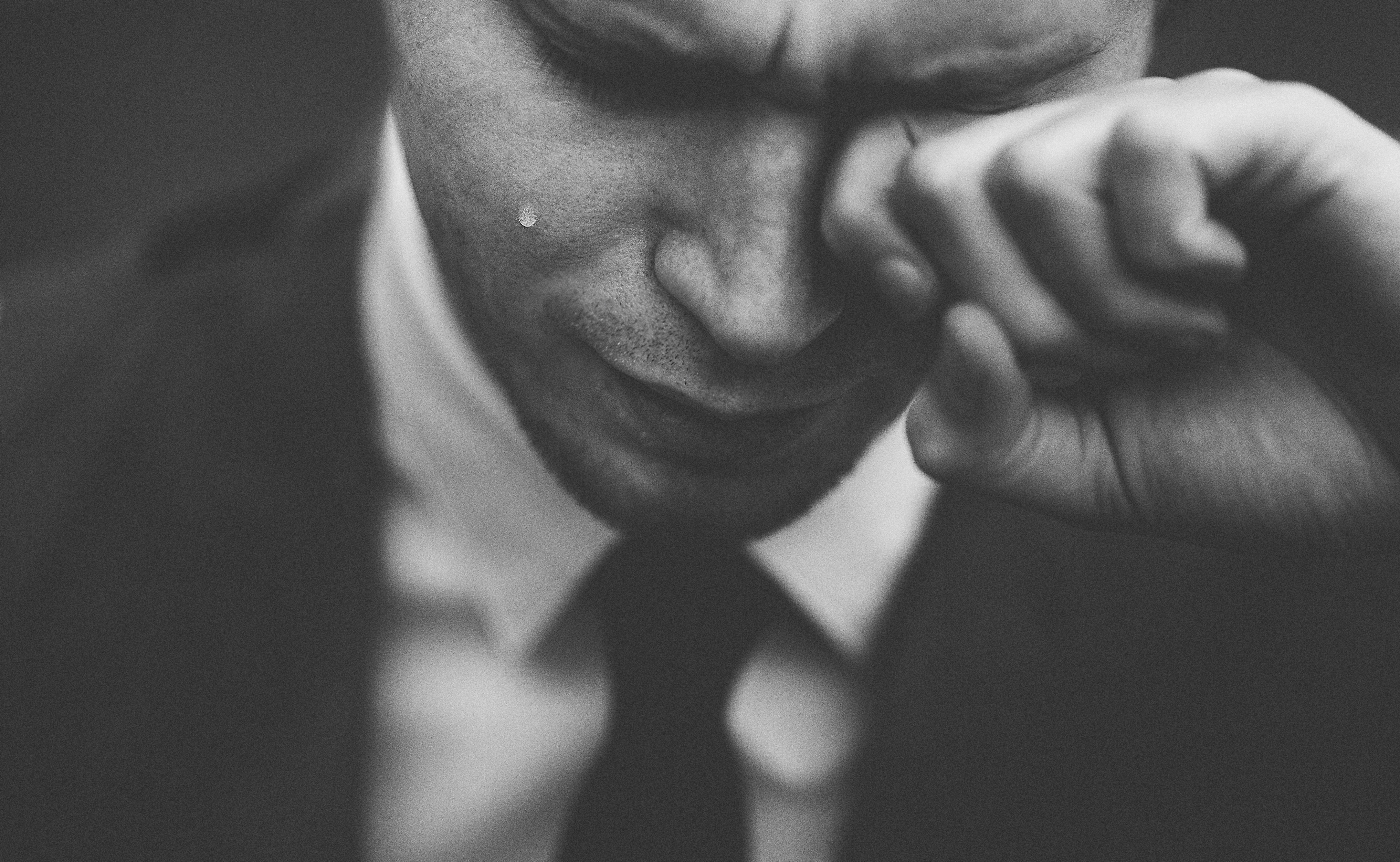
本当は泣きたいのに、泣かないでいると、心の病の原因になる事もあります。
以前カウンセリングでこんな事例がありました。
30代後半女性。「最近自分がおかしいと思うのです」と相談に来られました。よく聞いてみると8ヶ月前にお父様が亡くなり喪主を務められたそうです。四十九日も終わり一周忌の準備をしようと思っても体が以前のように動かず困っているとのことでした。
ご本人は体の病気を疑って相談に来られたのですが、症状を伺ってもあまりハッキリしないものが多く、朝起きると体が重くて動けないと言うのです。
「お父様が亡くなった後ちゃんと悲しみましたか?ちゃんと泣きましたか?」とお聞きしました。
「え?でももう8ヶ月も経っていますよ!」最初は驚いた表情でしたが、すぐに涙ぐんで「そういえば周囲のことばかり気にしていて自分が悲しむことをしていなかったかもしれません。」
それからその方は、相談室で少しの間泣くことができました。時間的には8ヶ月が経過していますが、この方にとってはその時の感情表現が8ヶ月遅れでようやく表現できました。
「朝、体が重くて動きたくない」というのは「このまま放っておくとうつ状態になるよ」というサインだったと思います。
感情を表現しないでいると、ストレスが蓄積していきます。その蓄積したストレスを抱えきれなくなると心が悲鳴を上げてうつ状態になっていきます。
悲しい時はちゃんと悲しむ。できればいっぱい泣くこと。泣くという行為は皆さんがこれからを元気に生きていくためには大切なことです。
感情を置き去りにして前に進もうとすると、心に負担がかかります。
カウンセリングで涙を流して心スッキリになりましょう!
女性ホルモン専門薬剤師の岡下真弓です。私は20年以上調剤薬局薬剤師として働いています。毎日様々な悩みを抱えた患者様が来られます。処方箋に記載されたお薬から、患者様が本当に悩まれていることを推測しながら、お薬の説明をすることで、その方のQOL(クオリティオブライフ:人生、生活の質))を高めることができます。私は患者様が笑顔で過ごす時間が少しでも長くなるよう、いつも接しています。
肩こり、やる気、膀胱炎…色んな不調の原因はコレだった!

とある日、50代女性が私の勤める薬局に、3枚の異なる病院の処方箋を持参されました。
処方箋1:精神科 「眠れない、やる気が出ない」
処方箋2:整形外科 「肩こり」
処方箋3:泌尿器科 「膀胱炎」
「今まで私はとても活動的だったの。でも最近何もする気がおきなくって。しかも、まったく疲れていないはずなのに 眠れない。もしかして鬱(うつ)なのかしら?」
「肩こりがひどくて何もやりたくない。スポーツジムに通っても、マッサージに通っても改善しない。骨に異常があるのでは?と思い、整形外科に行ってレントゲン撮ったけどどこも悪くないって。」
「すぐに膀胱炎になるのよ。頻尿でトイレも近くて友達と出かけるのが恥ずかしく、水分摂るのを控えているんだけど。」
様々な不快な症状に悩まされ、ふさぎがちになり、外出もままならないとのこと。
今まで元気だった自分と違いすぎて、自分の現状を受け入れられないご様子でした。
一見別々の症状で、色んな病院を巡っては原因が分からず不安を抱えてらっしゃいました。
実は、これらの別々の症状の原因は、コレだったのです。
「女性ホルモン(エストロゲン)の減少」です。
なぜ女性ホルモンが減ると色んな症状が出るのか?

なぜ女性ホルモン(エストロゲン)が減少することで、これらの様々な症状が出てくるのでしょうか?
1.うつ症状や不眠の原因
更年期世代の寝つきの悪さに エストロゲンが大きく関係しています。
更年期以降の女性で、以下のような睡眠の悩みを抱える女性が増えますが、寝つきの悪さのみであれば、エストロゲンの欠乏が考えられます。
・熟睡感がない
・睡眠時間が短い
・途中で目覚めてしまう
これらの睡眠の質の悪化は 生活の質にも影響します。
2. 肩こりの原因
エストロゲンは骨量を維持する作用があります。
女性は男性に比べ、閉経前後に著しい骨量の低下が見られます。この骨量低下が酷い肩こりを引き起こしている可能性があります。
さらに、エストロゲン減少に伴う骨量低下は、顔のたるみを引き起こすため、更年期を境に、急に体内だけでなく、見た目の老化も加速します。
3. 膀胱炎の原因
膀胱や尿道は、神経の命令によって、蓄尿・排尿をコントロールしています。
これらの働きにより、尿をためたい時は漏らさず、出したいときは残らず出し切ることができるのです。また膀胱は、伸び縮み可能な筋肉の袋なので、本来なら尿を貯める機能が備わっています。
ところが、老化に伴う筋肉の衰えに加え、エストロゲンの低下によって、排尿困難と排尿障害を招くことがあります。
先ほどの女性は、膀胱括約筋の影響により、頻尿・膀胱炎を繰り返していたのです。
更年期世代の女性に必要なこと
更年期前後の女性には、閉経に伴う心身の大きな変化がおこり、戸惑う方が多くみられます。
私は、先ほどの女性にこのようにアドバイスいたしました。
「すぐにかかりつけの婦人科医師を見つけ、受診してください。」
なぜならば、最近の婦人科では、がん検診もでき、性生活や、精神的な悩み、女性有の様々なサポートを受けることができるからです。
その女性は 婦人科を受診され、漢方薬の処方箋を持参されました
今では、謎の症状の原因が分かり、笑顔と健やかな生活を取り戻されました。
病院や薬に頼るまでではないという方は、以下のような食材を積極的に摂取しましょう。
・大豆製品(豆腐、納豆、豆乳、おからなど)
・たんぱく質(肉、魚、卵、チーズ、ヨーグルト、大豆など)
閉経前後の女性に伝えたいこと

女性は、閉経に伴う心身の大きな変化がおこります。また親の介護、夫の定年、子供の自立などネガティブイベントも多くなります。
更年期といえば、イライラ、ホットフラッシュをイメージされる方が多いようでが、初期に現れやすい症状は、骨量低下に伴う顔のたるみです。
1人で決して悩まず、婦人科医、薬剤師、看護師など身近に相談できる人を見つけおきましょう。
また更年期以降に検査して、初めてわかる疾患もあります。早期発見により予防や治療を行うことができます。私もその一人です。
いつも患者様に私は伝えます。
「更年期はターニングポイントにすぎません。更年期以降の人生を 楽しく健康的に暮らしていくためにその不快な症状は、身体があなたに知らせてくれた サインと思ってください。歳を重ねる事をネガティブにとらえず、ありのままの自分をたくさん愛していきましょう。 あなたのこれからの人生のために。」

