マッサージを受けた翌日、身体にだるさや痛みを感じたことがある人もいるのではないでしょうか。
身体の不調改善やリフレッシュのためにマッサージを受けたのに、上記のような症状が現れてしまうとびっくりしてしまいますよね。
マッサージ翌日に起きる身体のだるさや痛みは、マッサージによる好転反応の可能性があります。
マッサージを受けた後の過ごし方に注意することで、身体が回復に向かっていきます。
マッサージを受けた後の過ごし方について「どんなことに気をつけたらいいんだろうか?」と疑問に思っている人もいるでしょう。そこで、この記事ではマッサージの好転反応についてや、マッサージを受けた後の注意点、過ごし方について解説していきます。好転反応と揉み返しの違いについても紹介しているので、マッサージ翌日のだるさが気になっている人は、ぜひ参考にしてみてください。
マッサージの直後・翌日にだるくなったり眠くなったりするのは好転反応です
マッサージを受けた直後や翌日、身体がだるくなったり眠くなったりするのは、身体が回復に向かう際に起きる好転反応です。
好転反応には4つの種類があり、それぞれ症状が異なります。
弛緩反応
弛緩反応は、マッサージによって筋緊張が解れ、血流の循環が促されることで起きる好転反応です。
老廃物などの毒素が全身を巡り、身体の各器官が対応しきれなくなることで、倦怠感や眠気・発熱・だるさといった症状が現れます。
通常、2〜3日程度で症状は落ち着きますが、症状が3日以上続く場合や、症状が辛く起きられないような状態の場合は医療機関に相談してください。
過敏反応
過敏反応は、かゆみや炎症、痛みを感じる症状のことです。マッサージによって筋肉の緊張が解れ、血流の循環が促されると、上記の症状が現れることがあります。過敏反応は、2〜3日程度で落ち着くことがほとんどです。過度な運動を避け、ゆったり過ごすことで症状は落ち着くでしょう。
排泄反応
排泄反応は、マッサージによって血流の循環が促され、体内に滞った老廃物や毒素が排出される過程で起きる反応です。発汗や発疹・ニキビ・吹き出物・排尿・排便などの症状が起きますが、デトックスに必要な症状なので、過度な心配はいりません。
しかし、下痢が続くような場合は脱水症状を起こす可能性があるため、こまめな水分補給を心がけてください。下痢や吐き気によって水分補給が難しいなど、症状がひどい場合は医療機関に相談しましょう。
回復反応
回復反応は、筋肉の緊張が解れることで、血流の循環が促されて起こります。発熱や腹痛・倦怠感・吐き気などの症状が見られ、マッサージ部位に痣ができることも…。
4つの好転反応は、一般的に2〜3日程度で解消します。しかし、症状の現れ方には個人差があり、3日以上好転反応が継続したり、症状が重く動けなくなったりするケースもあります。好転反応の症状で心配がある場合は、医療機関に相談してください。
マッサージ後に注意するべきだるさとは

マッサージ翌日に起きるだるさは好転反応によるものだとご説明しましたが、同じようにだるさや痛みでも、注意しなくてはいけないものがあります。
それは、揉み返しです。
揉み返しは、マッサージの強さや方法などが原因で、筋肉がダメージを受けたときに起こります。
好転反応は身体が回復のために起きる症状でしたが、揉み返しは筋肉がケガを負っているサインといえるでしょう。
揉み返しと好転反応の大きな違いは、症状が起きる場所にあります。揉み返しはマッサージをした場所に痛みやだるさが現れますが、好転反応の場合は特定の場所ではなく、全身症状であることがほとんどです。また、好転反応は2〜3日程度で症状が消失しますが、揉み返しは3日以上、場合によっては1週間痛みを引きずることも珍しくありません。
揉み返しが起きたら、痛みや炎症が起きている場所を保冷剤などで冷やし、症状が収まるまで安静にしていましょう。揉み返しの症状がある状態で運動をしたり、症状のある部位を温めると、状態が悪化してしまう可能性があるので注意してください。
また、刺激の強いマッサージや長時間のマッサージ、未熟な施術者によるマッサージを受けると、揉み返しになってしまう可能性が高いです。
とくに、普段マッサージを受け慣れていない人は、揉み返しになりやすいので、上記のポイントに注意しましょう。
マッサージの後の過ごし方・してはいけないこととは?

マッサージを受けた後は、ゆったりと過ごすのがおすすめです。しかし、実際のところ、どんな風に過ごしたらいいのかわからないという人は多いでしょう。そこで、マッサージを受けた後のおすすめの過ごし方についてご紹介します。
軽い運動をする
マッサージを受けた後は、過度な運動を避けることが推奨されています。マッサージ後は身体が想像以上に疲労している上、普段以上のパフォーマンスを発揮できるせいで、ケガにつながりやすいからです。
しかし、マッサージ後に軽い運動をすることで、デトックス効果を促進できます。そのため、マッサージを受けた後はストレッチやウォーキングなど、軽く汗ばむ程度の運動を行うのがおすすめです。
ゆっくり休息を取る
マッサージを受けた後は、副交感神経が優位になっているため、通常よりも回復力が高い傾向にあります。回復力をより高めるには、ゆっくりと休息を取るのがおすすめです。睡眠時間だけでなく、睡眠の質にもこだわることで、身体の調子をより良い状態に整えられます。
こまめな水分補給を心がける
マッサージを受けた後は、身体に滞った老廃物や水分の排出が促されます。
デトックス効果を高めるためには、こまめな水分補給で老廃物の排出を助けてあげるのがおすすめです。
ただし、カフェインの多いコーヒーや紅茶・アルコール・ジュースは、デトックス効果を阻害してしまうのでおすすめできません。
マッサージ後の水分補給には、水やノンカフェインの麦茶・小豆茶・ルイボスティーなどを選ぶといいでしょう。
長風呂を控える
マッサージは、普段使わない筋肉を手技や機械で動かしているため、身体がいつもよりも疲れています。マッサージ後に長時間のお風呂に入ると、身体がさらに疲れてしまうので避けたほうがいいでしょう。また、マッサージ直後の入浴もおすすめできません。
しかし、マッサージ後に汗をかくことでデトックス効果を促進できるため、施術から2〜3時間後以降に、軽い半身浴をするのはおすすめです。
同一姿勢を避ける
せっかくマッサージを受けても、同じ姿勢を長時間続けていると、身体がすぐ凝り固まってしまいます。マッサージを受けた後は、座りっぱなしや立ちっぱなしなどの同一姿勢は避けましょう。
また、マッサージで身体の歪みを治しても、いつもと同じ姿勢を続けていたら、すぐ元の状態に戻ってしまいます。いつもカバンを同じほうの手で持っている、歩き方や立ち方に癖があるという人は、マッサージを機に姿勢の見直しをするのがおすすめです。
まとめ
本記事では、マッサージの翌日に起こる好転反応の特徴や、揉み返しとの違い、マッサージ後の過ごし方について解説しました。
マッサージを受けた後は、身体を回復するためにだるさや痛みなどの好転反応が起きる場合があります。通常好転反応は2〜3日程度で症状が治まりますが、症状が長期間続く場合や重い場合は医療機関に相談するのがおすすめです。また、マッサージ後はしっかりと休息を取り、身体の回復機能を高める必要があります。過度な運動や長時間の入浴は避け、ゆったりと回復力を高めましょう。
こんにちは!千葉市でうつ病回復支援専門カウンセラーをしております吉川淳子です。
私は保健師資格もあるので皆さんの心身両面のアドバイスができます。企業での健康管理経験からうつ病で休職・復職した方のサポートも多数させていただいております。
皆さんがメンタル不調にならないためにはストレスを溜めないように自己管理することが大切ですよね。ここでは誰でもできる簡単なストレス解消法をお伝えします。
涙はストレスを流してくれる

嬉しくて泣く、悲しくて泣く、悔しくて泣く、感動して泣く。
実は、『涙』の中にストレス物質が含まれています。泣く事で、ストレス物質が体の外に出ていきます。
感情が動いて出る涙と、玉ねぎを切っている時に出る涙とは、成分が少し異なります。
感情が動いて出る涙には、ストレス物質の副腎皮質ホルモン「コルチゾール」などが流れ出ています。
それだけでなく苦痛を和らげる物質も出てくるので「あー泣いたらスッキリした!」という状態になるのです。
ということは、感情が動いているのに、泣くのを我慢するとストレスが自然に出ていくのを止めてしまうという事になります。状況にもよりますが、出来るだけ涙は流してしまった方が良いですね。
中でもストレス解消効果が高いのは、ポジティブな感情が動いた時の涙と言われています。
ラグビーのトライが決まった瞬間やフィギュアスケートで逆転勝利した瞬間など選手と一緒に流す涙は心身ともにスッキリすること間違いなしです。
なかなか泣けない時はどうする?

ストレス解消したいから涙を流そうと思っても、感情を動かすことが起きなければなかなか難しいことですよね。
ストレスが溜まっているけど、泣けない方は、わざと泣く状況を作ってみるとよいです。
- 泣ける映画を観る
- 泣ける小説を読む
- 泣ける音楽を聴くな
- もしあればご自分が子供の頃に書いた作文や日記、家族写真なども意外と感動します
- 悲しかったこと、悔しかったことなどを、文字にして読んでみる
- 親しい友人などに話しを聞いてもらって泣くのはとても効果的です
ネガティブな感情からの涙はあまり良くないと言う人もいますが、今の感情をタイムリーに涙と言葉で出してしまうのはストレスを溜め込まないためにはやった方が良いのではないかと思います。
泣く場所も考え物ですよね?車の中、お風呂、寝る前の布団の中、海岸、公園など、ひとりになれる場所を見つけてみてください。
私のカウンセリングルームでは思いっきり泣けます!
ちゃんと泣かないと心の病に!?
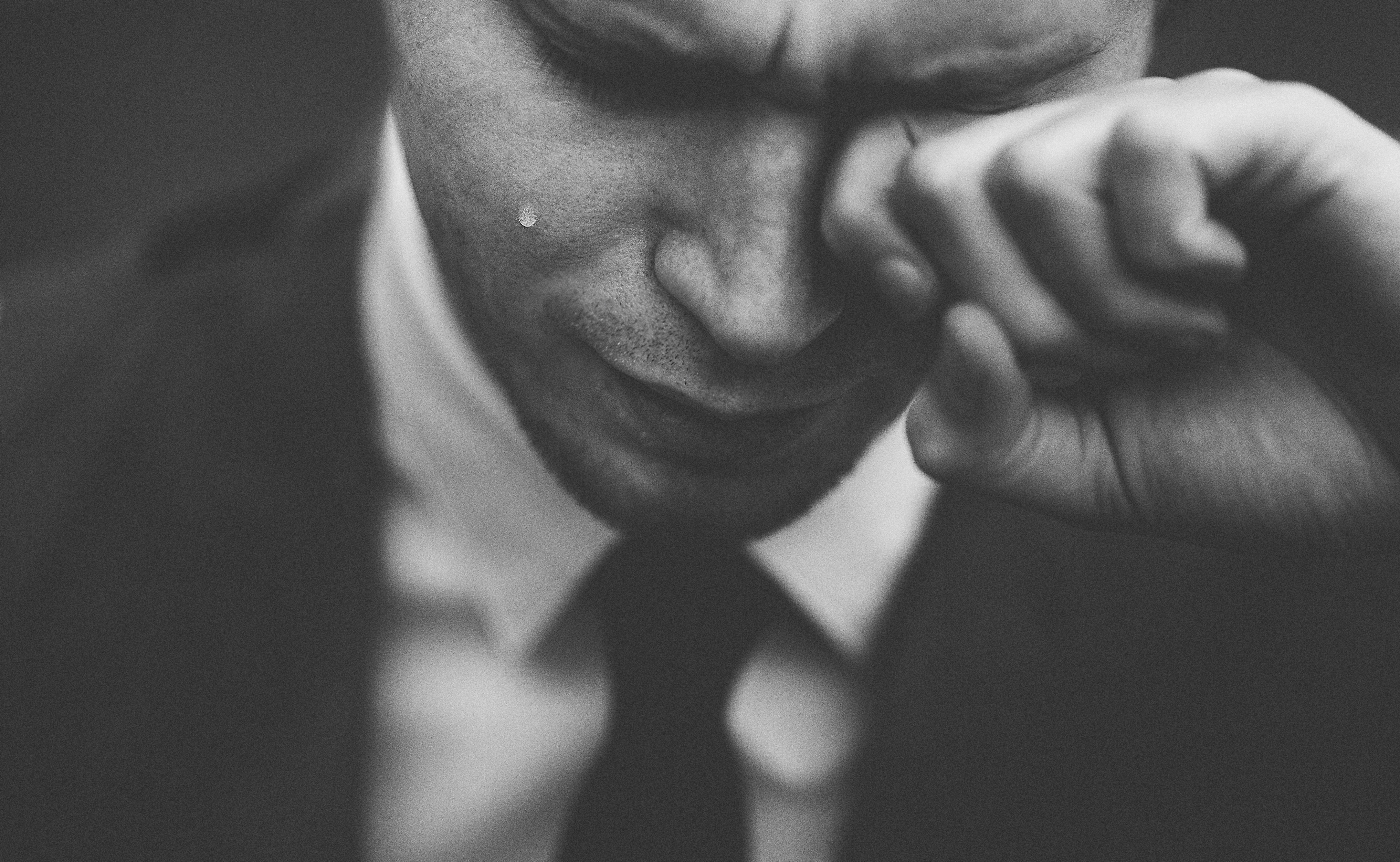
本当は泣きたいのに、泣かないでいると、心の病の原因になる事もあります。
以前カウンセリングでこんな事例がありました。
30代後半女性。「最近自分がおかしいと思うのです」と相談に来られました。よく聞いてみると8ヶ月前にお父様が亡くなり喪主を務められたそうです。四十九日も終わり一周忌の準備をしようと思っても体が以前のように動かず困っているとのことでした。
ご本人は体の病気を疑って相談に来られたのですが、症状を伺ってもあまりハッキリしないものが多く、朝起きると体が重くて動けないと言うのです。
「お父様が亡くなった後ちゃんと悲しみましたか?ちゃんと泣きましたか?」とお聞きしました。
「え?でももう8ヶ月も経っていますよ!」最初は驚いた表情でしたが、すぐに涙ぐんで「そういえば周囲のことばかり気にしていて自分が悲しむことをしていなかったかもしれません。」
それからその方は、相談室で少しの間泣くことができました。時間的には8ヶ月が経過していますが、この方にとってはその時の感情表現が8ヶ月遅れでようやく表現できました。
「朝、体が重くて動きたくない」というのは「このまま放っておくとうつ状態になるよ」というサインだったと思います。
感情を表現しないでいると、ストレスが蓄積していきます。その蓄積したストレスを抱えきれなくなると心が悲鳴を上げてうつ状態になっていきます。
悲しい時はちゃんと悲しむ。できればいっぱい泣くこと。泣くという行為は皆さんがこれからを元気に生きていくためには大切なことです。
感情を置き去りにして前に進もうとすると、心に負担がかかります。
カウンセリングで涙を流して心スッキリになりましょう!

