ヘアケア用品の一つとして愛用している方も少なくないナイトキャップですが、ネット上では就寝時のナイトキャップは逆効果なのではないかと話題になっています。
本当のところはどうなのでしょうか?
そこで本記事では、
- ナイトキャップが逆効果と言われている理由
- ナイトキャップの正しい使い方と効果
- おすすめのナイトキャップと選び方
上記3点を中心にナイトキャップの効能について詳しく解説していきます。
ナイトキャップは逆効果?逆効果とネット上で言われているワケとは
ナイトキャップの性質とネット上で逆効果なのではと言われている理由について解説します。
ナイトキャップとは
ナイトキャップは、名前のとおり「就寝時にかぶる帽子」です。シラミや寒さ対策として欧州から伝わってきました。寝返りの際に帽子が脱げないよう、ゴムの強度を調節できるようになっています。
就寝時に髪と枕の摩擦を防ぎ、髪へのダメージ軽減が期待できる点が特徴です。
ナイトキャップは逆効果と言われている理由
ナイトキャップが髪に対して逆効果と言われている理由には以下の3つが挙げられます。
- 髪が密閉状態になり、蒸れるのが気になる
- 蒸れると雑菌が繁殖し、頭皮環境の悪化につながる恐れがある
- 帽子で髪が固定されるため、逆に寝ぐせがつきやすい
上記のような理由から、ナイトキャップは逆効果なのではないかと言われています。
ナイトキャップの効果・デメリットとは?口コミもご紹介!

ナイトキャップを使うと髪にどのような効果・デメリットがあるのでしょうか。また、ナイトキャップに関する口コミも合わせてご紹介します。
ナイトキャップの効果
ナイトキャップには以下の4つの効果があります。
- 髪と寝具の摩擦を軽減
- 髪や頭皮の乾燥を防ぐ
- 寝ぐせや髪の絡まりを防ぐ
- 季節ごとの寒暖差対策
髪と寝具の摩擦を軽減
髪は就寝中に寝返りを打つと枕とこすれて摩擦によりダメージを受けてしまいます。ナイトキャップをかぶることで、髪と枕が直接接触するのを防ぎ、ダメージの軽減につながります。また、寝具のダニや害虫などの予防対策としても活用できる点もメリットです。
髪や頭皮の乾燥を防ぐ
就寝中、髪や頭皮の水分は温度や湿度の関係で失われていきます。しかし、ナイトキャップ内は一定の温度・湿度が保たれるため水分の蒸発を防ぐことができます。水分量が保たれることで、起きるまでまとまりのある髪をキープできるというわけです。
寝ぐせや髪の絡まりを防ぐ
寝返りによって髪が乱れ、枕に押さえつけられることで寝ぐせや髪が絡まる要因になります。ナイトキャップは帽子内に髪をまとめるため、寝返りを打っても髪が乱れることが少ないです。そのため、起床時の寝ぐせや髪の絡まりを防ぐことができます。
季節ごとの寒暖差対策
ナイトキャップは冬場の寒さ対策はもちろんですが、夏場の暑さ対策にも活用できます。ロングヘアーの方は髪をすっきりとまとめられるため、首元の不快感が軽減するでしょう。また、ナイトキャップには通気性や吸水性に優れる物もあるため、季節によって使い分けができます。
ナイトキャップのデメリット
デメリットとしては、以下の3つです。
- 使い方を誤ると頭皮環境の悪化につながる
- 間違ったかぶり方は、逆に寝ぐせがつきやすい
- サイズが合っていないと脱げやすい
それぞれの解決法については後ほど詳しく解説していきます。
ナイトキャップの良い口コミ
- 寝起きの髪の毛がしっとりとまとまるようになった
- 髪の状態を気にすることなく気軽に寝返りが打てるようになった
- 髪のまとまりが良くなって、朝のスタイリングが楽になった
ナイトキャップの悪い口コミ
- 夏場は暑くて頭に寝汗をかいてしまう
- 寝ている間に脱げてしまっている
- 起きると帽子のゴム跡がついている
ナイトキャップに向いている人・向いていない人の特徴とは
ナイトキャップに向いている人の特徴は以下の3つです。
- ヘアケアに一層力を入れたい
- 髪の乾燥やパサつきに悩んでいる
- 寝起きの髪の状態を改善したい
一方、ナイトキャップに向いていない人の特徴は以下の3つです。
- ヘアケアに興味がない
- 髪の状態で特に悩みがない
- ナイトキャップをかぶって寝ることに抵抗がある
また、ナイトキャップはメンズにも効果があります。冬場の乾燥は髪のパサつきや頭皮の乾燥を招くため、保湿性の高いナイトキャップはメンズにとっても有効です。ただし、男性は頭皮の皮脂量が多いため、夏場でナイトキャップを使用する際には通気性や吸水性の高いものを選ぶようにしましょう。
ナイトキャップの逆効果となる使い方とは?正しいかぶり方を解説!
ナイトキャップの効果を実感できないという方は、もしかしたら間違った方法で使用しているかもしれません。ここでは、ナイトキャップの逆効果となる使い方と正しい使い方の両方をご紹介します。
逆効果となるナイトキャップの使い方
逆効果となるナイトキャップの使い方には以下の4つがあります。
- 髪が濡れた状態で使用
- 頭のサイズや毛量に合っていないものを使っている
- 帽子の中に無理やり髪を入れ込んでいる
- 季節や環境に関係なく同じ物を使用している
髪は濡れているとキューティクルが開いた状態になります。この状態は、髪の中の水分やタンパク質が外に出ていってしまうため、傷つきやすくクセもつきやすいです。また、濡れたままナイトキャップをかぶってしまうと、湿気がこもり蒸れてしまいます。その結果、雑菌が繁殖し、頭皮環境のトラブルを招いてしまいかねません。
寝ている間に帽子が脱げてしまうという方は、頭の大きさや毛量に対してサイズが大きすぎるのが原因です。また、朝起きたときに、帽子の跡がついてしまう理由もサイズが合っていないことが考えられます。
ナイトキャップはかぶり方がもっとも重要です。無理やり入れ込んでしまうとクセがついたり、逆に傷んでしまう原因になってしまいます。そのため、正しいナイトキャップのかぶり方を知ることが大切です。
寝ている間しか使わないからといって季節や環境に関係なく同じものを使用していませんか。ナイトキャップにはさまざま種類や素材の物があります。夏場には大量の汗をかくため、通気性や吸水性の悪い物では逆効果になってしまいます。
正しいナイトキャップの使い方
正しいナイトキャップの使い方は以下の3点です。
- 髪をしっかり乾かした状態でかぶる
- 頭のサイズに合った物を使う
- 毛流れに逆らわずに髪を入れ込む
- 季節や環境に合った物を使う
それぞれ説明していきます。
髪をしっかり乾かした状態でかぶる
髪をしっかりと乾かして、水分と栄養を髪の内側に閉じこめた状態でナイトキャップをかぶるようにしましょう。そうすることで、ナイトキャップ本来の役割である髪に潤いとまとまりを保ったまま朝を迎えられるようになります。
頭のサイズに合った物を使う
頭のサイズに合ったものを見つける際には、ゴムやヒモで強度を調節できる物がおすすめです。逆に小さすぎて髪に跡ができてしまう方は、フリーサイズの物か伸縮性のゆるいゴムに取り替えることで解決できます。
また、ツルツルとした素材は肌触りが良い分、脱げやすいです。そのため、帽子と髪をヘアピンなどで固定するとよいでしょう。ヘアバンドやヒモで縛るタイプの物は脱げにくいためおすすめです。
毛流れに逆らわずに髪を入れ込む
ナイトキャップをかぶるときの悩みとして「かぶり方がわからない」という方が多いです。
順を追ってナイトキャップのかぶり方を解説していきます。
- 髪を下した状態でナイトキャップをかぶる
- (ロングヘアの場合は)片手で髪をまとめる
- 手とまとめた髪を一緒に帽子に入れ込む
- もう片方の手で押さえながら、手を引き抜く
- 全体を整えながら、外に出ている髪を帽子に入れ込んで完成!
帽子に押さえつけられて、前髪がぺったんこになってしまうのを避けたい場合の対処法についてご紹介します。前髪をまっすぐにおろさず、毛流れに沿って少し斜めに流して入れ込むようにしてください。また、前髪が短い場合は出してから被っても問題ありません。
季節や環境に合った物を使う
ナイトキャップは前述のとおり寝ぐせや寒暖差、髪の乾燥対策になるため、冬や乾燥時期にはおすすめです。しかし夏場は寝汗が増えて頭皮環境を悪化させる可能性もあります。そのため、夏など暑い季節に寝汗で寝苦しく感じるという方は、リネン(亜麻を加工して作った布素材)のナイトキャップにすると、通気性が良いでしょう。
シルクは湿度を調整してくれるため、季節を問わず使えます。冬に空気が乾燥している時期、夏のクーラーで乾燥している部屋では湿度を保ってくれます。また、静電気が起こりにくいのもシルクの良いところです。
シルク?コットン?おすすめのナイトキャップをご紹介!
ナイトキャップの素材は大きく分けて「シルク」と「コットン」の2種類があります。
それぞれの特徴と髪の長さに合った選び方をご紹介します。
シルク素材は、吸湿性と保湿性に優れ、蒸れにくく肌触りが良いのが特徴です。シルクの中でも合成と天然のものがあり、天然シルクはタンパク質と油分を豊富に含んでいるため、髪にツヤを与えてくれます。髪に指通りの良さとツヤが欲しい方にはシルクがおすすめです。
デメリットとしては、生地が傷みやすく、お手入れに手間がかかってしまう点です。
コットンの特徴は、吸水性と通気性に優れ、生地の丈夫さからお手入れがしやすいのが特徴です。髪の有効成分ではシルクに劣る点はありますが、高い吸水性と通気性でしっとりとした髪の質感が欲しい方はコットンを選びましょう。また、シルクに比べ手ごろな価格で買える点も魅力です。
ここからは、髪の長さに合ったサイズや商品の選び方について解説していきます。
ロングヘアの方は、髪を入れ込みやすく、脱げにくい「ゴムタイプ」がおすすめです。伸縮性があるため、後れ毛や周りの髪をしっかりと入れ込めます。一方、ゴムの強度を調節できない物が多く、跡がつきやすい点がデメリットです。
また、髪の長さや頭の大きさに合わせて調整ができる「リボンタイプ」もあります。締め付けの強度を調節できる点が魅力ですが、結び方が緩いと脱げやすい点には注意が必要です。ロングヘアの方は、リボンを結ぶ際に髪が出てきてしまうことがあるため、使いづらいと感じた場合はゴムタイプを検討しましょう。
おすすめのナイトキャップ3選
おすすめのナイトキャップをご紹介します。
LILYSILK(リリーシルク)19匁天然シルク100% ナイトキャップ|4,400円(税込)

LILYSILK(リリーシルク)19匁天然シルク100% ナイトキャップは、6Aランクのシルクを贅沢にしたナイトキャップです。6Aとはシルクのランクの中でもっとも高い品質に位置しています。19匁とはシルクの重さを表す単位で、約72gになります。ショートからロングヘアの方まで使いやすいゴムタイプとなっており、昨夜のトリートメント効果が朝まで続くと評判のナイトキャップです。
Amazonで見る>>
Omahit 天然シルク100% ナイトキャップ|1,780円(税込)
Omahit 天然シルク100% ナイトキャップは、6Aランクのシルクを使用した品質の高いナイトキャップです。リボンとゴムを組み合わせたタイプになっているため、髪の長さや頭のサイズに合わせたサイズ調整ができる点が魅力です。仕上がりとしては、ツヤのあるさらさらとした手触りになるため、シルクのナイトキャップの効果を実感できるでしょう。
HAHONICO(ハホニコ)シルクMoon ナイトキャップ|2,750円(税込)
HAHONICO(ハホニコ)シルクMoon ナイトキャップは、天然100%シルクを使用した最高品質のナイトキャップです。帽子が筒状になっており、髪を折らずに入れ込めるのが特徴で、特にロングヘアの方におすすめの商品となっています。
ナイトキャップのお手入れ方法
ナイトキャップの品質を保つためのお手入れ方法をご紹介します。
洗う頻度は、冬場は3~4日おきに洗うようにしましょう。夏場は、汗をかく量が多いため1~2日おきに洗うと清潔な状態を保てるでしょう。
洗い方は、シルク素材の洗い方を解説します。コットンはそのまま洗濯ができますが、シルクは傷みやすいためです。
- 桶に30℃以下の水かぬるま湯を入れて、中性洗剤またはシルク専用の洗剤を溶かします
- 布地を裏返しにして、やさしく手洗いしてください
- 2~3回、洗剤が落ちるまで十分にすすぎます
- 絞らずにバスタオルなどで押さえながら、水気を取ってください
- 直射日光を避けて、陰干ししてください
商品が傷んでしまい、起床時に髪のまとまりやツヤを感じられなくなった場合は、買い替えを検討しましょう。
まとめ
ナイトキャップは、
- 髪が濡れた状態で使用
- 頭のサイズや毛量に合っていないものを使っている
- 帽子の中に無理やり髪を入れ込んでいる
- 季節や環境に関係なく同じ物を使用している
上記の誤った使い方をした場合、逆効果になります。
対して、
- 髪をしっかり乾かした状態でかぶる
- 頭のサイズに合ったものを使う
- 毛流れに逆らわずに髪を入れ込む
- 季節や環境に合った物を使う
といった正しい使い方をすれば、きちんと効果が得られます。
本記事を参考に、ナイトキャップをヘアケアの一つに取り入れてみてはいかがでしょうか。
「ヘアオイルを寝る前につけると本当にはげるの?」
「ヘアオイルをつけるタイミングや使い方がわからない」
髪を乾燥から守るために使うヘアオイルですが、上記のような疑問や悩みを持っている方も多いのではないでしょうか?
寝る前のヘアオイルが本当に効果的なのかどうか、その真相を知っておきたいですよね。
そこでこの記事では、ヘアオイルを寝る前につけることのメリットや効果的なヘアオイルの使い方をご紹介します。おすすめのヘアオイルもいくつかご紹介していきますので、是非参考にしてください。
ヘアオイルを寝る前につけるとはげるって本当?
たまに「ヘアオイルを寝る前につけるとはげる」という噂を聞きますが、寝る前にヘアオイルをつけるだけではげる可能性は低いです。
しかし、頭皮に合わない成分のものを使用したりすると、頭皮が荒れてしまい頭皮環境が悪化し、抜け毛につながる可能性はあります。
基本的にヘアオイルは頭皮ではなく毛先に塗るものですので、寝る前に塗ることで直接的にはげるという原因には繋がらないのです。
寝る前に頭皮からべったりとヘアオイルを塗り、そのことで頭皮が荒れてしまい、抜け毛などに繋がってしまうことから「寝る前のヘアオイル=はげる」という噂が始まったのでしょう。
ヘアオイルを寝る前につけるメリットとは?
実はヘアオイルを寝る前につけるのはたくさんのメリットがあります。
- 寝ている間の髪の毛の乾燥を防止
- 寝ぐせを抑えて朝の身支度が楽になる
- 髪の毛のダメージを軽減してくれる
上記3つのメリットがありますので、一つずつ詳しくご紹介していきます。
寝ている間の髪の毛の乾燥を防止
ヘアオイルを寝る前に付けるメリットの一つは「乾燥を防いでくれる」という点があります。
就寝中の髪の毛は水分を失いやすく、乾燥の原因になってしまいます。
夏や冬の時期にエアコンを付けながら寝ると、余計に髪の毛が乾燥してしまい、朝起きると髪の毛がパサパサになってしまう、といった経験をしている方も多いでしょう。
そこで寝る前にヘアオイルをつけることで、髪の毛をコーティングし、水分を保持することで乾燥しにくい髪の毛にすることができます。
寝ぐせを抑えて朝の身支度が楽になる
寝る前にヘアオイルをつけることで、髪の毛の広がりを抑えてくれ、寝ぐせがつきにくいというメリットがあります。
よく寝ぐせがついて「朝の身支度が大変…」と感じている方は、寝る前にヘアオイルをつけるだけで、朝のスタイリングが楽になるでしょう。
またヘアオイルに含まれている髪への美容成分が寝ている間に浸透し、朝起きると良い状態の髪の毛で1日を始めることができます。
寝ぐせ直しの時間を何とかしたいと思っている方は、是非寝る前のヘアオイルを試してみてください!
髪の毛のダメージを軽減してくれる
髪の毛は摩擦や乾燥した空気の影響をとても受けやすいです。
エアコンの空気や寝返りによる枕との摩擦などによって、ダメージを受けやすいのですが、ヘアオイルで髪の毛をコーティングすることによってそれらのダメージから髪の毛を守ってくれます。
ダメージヘアに悩んでいる方は、寝る前のヘアオイルによって髪質を良くできるというメリットがあるのです。
ヘアオイルをつけるのはドライヤー後が効果的?寝る前の使い方をご紹介
ヘアオイルを寝る前につける場合は、ドライヤーをした直後がおすすめです。
ここからはヘアオイルの正しい使い方や、ヘアオイルを使う際の髪型に合った適切なヘアオイルの量について解説していきます。
効果的な寝る前のヘアオイルの使い方は以下の通りです。
お風呂上がりは髪の毛をタオルドライ
- ブラシで毛先まで髪の毛をとく
- ドライヤーで髪の毛を乾かす
- ヘアオイルを髪の毛の長さに合わせて適量取る
- 手になじませ、髪の中間から毛先にかけてなじませる
お風呂上りは、髪の毛に水分がたっぷり保たれた状態となりますので、そのタイミングでヘアオイルをつけることをおすすめします。
またドライヤー前とドライヤー後でヘアオイルを付けるタイミングが違う、という方がいますが、寝ている間の乾燥やダメージから髪の毛を守るなら「ドライヤー後」がおすすめです。
髪の毛が乾いた状態でなじませると、髪の毛の表面がコーティングされ、ツヤのある仕上がりになります。
ヘアオイルの適切な使用量
ヘアオイルをつける際の量ですが、髪の毛の長さに合った適量を付けなければ、効果的とはいえません。
使用量が多すぎると髪の毛のべたつきや頭皮トラブルに繋がったり、少なすぎると乾燥防止が不十分になってしまうといえるでしょう。
髪の長さに合わせた量を使用することをおすすめします。長さ別の使用量は以下の通り。
| 髪の長さ | ヘアオイルの量 |
|---|---|
| ショートヘア | 1滴~2滴 |
| ミディアムヘア | 2滴~3滴 |
| ロングヘア | 3滴~4滴 |
適量を守り、正しく使用して美しい髪の毛を維持しましょう。
ヘアオイルを寝る前につけるときの注意点を解説!
ヘアオイルを寝る前につけるときに注意しておきたいのが「ヘアオイルが枕につく」という点です。
枕にヘアオイルがついてしまい、肌にヘアオイルが付着してしまうと、ニキビができる原因となってしまう可能性があります。
ヘアオイルにはオレイン酸と呼ばれる成分が含まれており、肌が敏感な方やニキビができやすい肌質の方だと、肌荒れの原因となってしまうのです。
ニキビが気になっている人には特に注意が必要ですが、枕にヘアオイルが付くのを防ぎたい方は、ネットキャップなどを頭にかぶって寝る事をおすすめします。
肌質や髪質に合わせて選ぼう!寝る前につけるヘアオイルの選び方を解説
寝る前のヘアオイルの使い方や注意点について解説してきましたが「どんな商品を選べばいいかわからない」という方も多いでしょう。
ヘアオイルには様々な種類があり、含まれている成分が商品によって異なります。
大きく分けて「植物性オイル」「動物性オイル」「鉱物性オイル」の3つがありますので、それぞれの種類のヘアオイルがどんな髪質や肌質に合っているのかを簡単に表でまとめました。
| ヘアオイルの種類 | 特徴 | こんな髪質におすすめ | こんな肌質におすすめ |
|---|---|---|---|
| 植物性オイル | 天然由来のオイル成分 | サラサラとした髪質 | 脂性肌・敏感肌 |
| 動物性オイル | 馬油などの動物由来 | ダメージの多い髪質 | 敏感肌 |
| 鉱物性オイル | 石油などから抽出したオイル | ごわつきのある髪質 | あらゆる肌質に対応 |
髪の毛が細い方や猫毛のようなサラッとした髪質の方は「植物性オイル」がおすすめです。
また、カラーやパーマなどでダメージを受けている髪質の方には、しっかりとしたツヤを髪の毛に与えられる「動物性オイル」がおすすめとなっています。
「鉱物性オイル」は揮発しにくいというのが特徴の一つですので、毛先までまとまった髪の毛に整えたい場合や髪質が太い方におすすめです。
このように、自分の髪質や肌質に合ったヘアオイルを選び、使用することで、より効果的に髪の毛を美しく保つことができます。
寝る前におすすめのヘアオイル3選
最後に寝る前に使用するのにおすすめのヘアオイルを3種類ご紹介していきます。
髪質や肌質に合った商品をご紹介していきますので、自分の悩みや目的に合ったものを選んでみてください!
パサつき・くせ毛に| エイトザタラソ リペアショット&EXモイスト 美容液オイル

幹細胞エキスと、海洋由来成分などを配合した「タラソ幹細胞処方」のヘアオイルです。
髪の毛の水分や油分のバランスを整え、髪に浸透するように馴染んでツヤを与えます。
パサつきやくせ毛が気になる髪質の方におすすめです。日々のスタイリングや、寝る前のヘアケアにも使える万能的なヘアオイルです。
| 商品名 | エイトザタラソ リペアショット&EXモイスト美容液オイル |
|---|---|
| 価格 | 1,540円(税込) |
| オイルの種類 | 植物性 |
| テクスチャー | サラサラ |
| 香り | アクアホワイトフローラル |
ダメージヘアに| ロレアルパリ エルセーヴ ヘアオイル エクストラリッチ フィニッシュ
6種類のフラワーオイルを配合したプチプラヘアオイルです。
アイロンやドライヤーなどによる熱ダメージや、カラーやパーマなどによって影響を受けたダメージにおすすめで、潤いたっぷりの髪質に仕上げることができます。
ドラッグストアで手に入るヘアオイルですので、お買い求めしやすく手軽に購入できるのが魅力の一つです。
| 商品名 | ロレアルパリ エルセーヴ ヘアオイル エクストラリッチ フィニッシュ |
|---|---|
| 価格 | 2,189円(税込) |
| オイルの種類 | 植物性 |
| テクスチャー | しっとり |
| 香り | フローラルバニラ |
敏感な髪質・肌質に|大島椿 椿油100% マルチオイル

天然椿油を100%使用したこちらのヘアオイルは、敏感肌の方やダメージを受けやすい髪質の方におすすめです。
天然成分で髪の毛に潤いを与えるだけでなく、無香料・無着色・無鉱物油ですので、肌荒れが心配な方でも安心して使用できます。
髪の毛・頭皮・肌に使用できるマルチオイルですので、寝る前のヘアケアだけでなく日々のスキンケアや頭皮ケアにも使える万能型のヘアオイルです。
| 商品名 | 大島椿 椿油100% マルチオイル |
|---|---|
| 価格 | 1,210円(税込)~ |
| オイルの種類 | 植物性 |
| テクスチャー | さらさら |
| 香り | 無香料 |
まとめ
本記事では、ヘアオイルを寝る前に使用することのメリットやヘアオイルの選び方、注意点などをご紹介してきました。
「ヘアオイルを寝る前につけるとはげる」というのは、根拠のない噂です。しかしヘアオイルの成分が肌質に合ってなかったり、適量を正しく使用できていないと抜け毛の原因になってしまうことがあるので注意が必要です。
自分の肌質・髪質に合ったヘアオイルを寝る前につけることで、就寝中のダメージから髪を守れたり、朝のスタイリングが楽になったりとメリットもたくさんあります。
本記事でご紹介したおすすめのヘアオイルも、様々な髪質や肌質に合うものをチョイスしていますので、是非参考にして自分に合ったヘアオイルを使いましょう!
乳液や化粧水を髪の毛や頭皮につけてもいいのかと疑問に思ったことはありませんか?
そんな化粧品の使い方の悩みを簡単に解決する方法があります。
この記事では、
髪に乳液や化粧水をつけるメリット
ヘアケアの代用品として使えるおすすめの乳液・化粧水
今日からできる簡単で効果的なヘアケア方法
上記の3点を中心に乳液や化粧水が髪に与える効能について解説していきます。
乳液や化粧水を髪の毛・頭皮につけてもいいの?その成分とは?
結論から言いますと、乳液や化粧水は髪の毛・頭皮につけても問題はありません。その理由は、乳液に含まれる成分にあります。
乳液の成分について
乳液は主に、以下の4つの成分が含まれています。
- 水分
- 油分
- 保湿成分(セラミド、ヒアルロン酸など)
- 界面活性剤(水分と油分を混ぜる乳化剤)
乳液は、水分と油分がベースとなっており、そのバランスが良いことが特徴です。セラミドやヒアルロン酸などの保湿成分には、肌だけでなく、髪の水分の蒸発を防ぐ働きがあります。
界面活性剤(乳化剤)は水と油の分離を防ぎ、乳化させる役割をもっており、保湿作用のサポートをしてくれます。ただし、界面活性剤は油汚れを落とす洗剤の成分として配合されていることが多く、敏感肌の方には刺激が強いものもあるため注意が必要です。
化粧水の成分について
化粧水も乳液と主な成分は似ていますが、その配合や水分が多めという所に違いがあります。
- 水分(水やエタノールなど)
- 油分(水に溶けにくいオイルや脂など)
- 界面活性剤(水分と油分を混ぜる乳化剤)
化粧水の成分は主に、水分、油分、界面活性剤の3つがベースになっています。そこに、顔料や粉体などの着色剤、機能性の成分(美白、抗酸化など)、使用感や香りをよくするもの、防腐剤や酸化防止剤などの品質を安定させる成分が加えられます。
化粧品のベース成分の中で、水分が多くを占めています。水分には、通常は精製水を利用しますが、メーカーによっては、温泉水、ハーブ水、海洋深層水などを加えている商品もあります。また、エタノール、グリセリン、ヒアルロン酸などリウム、コラーゲン、BG(ブチレングリコール)、DPG(ジプロピレングリコール)、PEG(ポリエチレングリコール)、ヒアルロン酸、糖類などの保湿をサポートする水分成分も使われます。
エタノールはさっぱり系の成分で、グリセリンはしっとり系の成分になり、それぞれのメーカーごとに、どれをどの程度配合するかでオリジナリティを出しています。
油分にも様々な種類があり、酸化のしやすさや、質感、保湿力もそれぞれの成分で異なります。例えば、オイル系は、スクワラン、ホホバオイルなど、ペースト状のこってり系はワセリンやシアバター、固めの質感のものだとミツロウやパラフィンなどがあります。
これらの油分と水分を界面活性剤で混ぜて乳化させています。
乳液や化粧水を髪の毛・頭皮につけるとどんなメリットがある?
乳液や化粧水を髪の毛・頭皮につけることには、以下の5つのメリットがあります。それぞれ解説していきます。
髪や肌を外的要因から保護
乳液に含まれる油分が、髪の外側をコーティングする働きによって、ドライヤーの熱や紫外線などの外的要因から髪や肌を保護してくれます。
熱や紫外線は髪のキューティクルをはがし、切れ毛やパサつきの原因にもなります。さらに、頭皮は太陽の紫外線の影響を大きく受けるため、毛根にもダメージが蓄積しやすく、抜け毛の原因にもつながります。
健康的なハリのある髪を維持するためには、熱や紫外線の対策は重要です。
乾燥の予防効果
乳液には水分を閉じ込め保湿する作用があるため、髪の毛の乾燥やパサつきの予防効果があります。
髪の毛や頭皮が乾燥する要因は「熱や紫外線」「季節の変わり目」「生活習慣」と多岐にわたります。外出時だけでなく頻繁にカラーやパーマをする方も、熱によるダメージで髪のキューティクルが傷んでパサつきの原因になっていることがあるため、注意が必要です。
健康毛の成長促進
乳液・化粧水は髪の毛だけでなく頭皮にも有効です。
頭皮の乾燥は「フケやかゆみ」の原因になり、頭皮環境の悪化から抜け毛を引き起こす要因にもなります。
頭皮の乾燥が気になる際には、化粧水で水分を補い、乳液で保湿をしてあげましょう。頭皮環境の改善は、健康な髪を育てることにつながります。
しかし、あくまで予防対策であって「必ず健康な髪が生えてくる」「抜け毛がなくなる」わけではないため、注意してください。
トリートメント効果
乳液には、セラミド・ヒアルロン酸をはじめとする保湿成分が多数含まれているため、ヘアケア用トリートメントの代わりとしても使用できます。
ヘアケア用トリートメントは、洗い流すタイプと流さないタイプがありますが、乳液はどちらの使い方もできるため好みに合った使い方ができる点もメリットです。
スタイリング剤の代わり
水分と油分のバランスが良い乳液は、スタイリング剤ほどセット力はありませんが軽いスタイリングや朝の寝ぐせ直しに使用できます。
そのまま使うとベタつきが気になる方は、スプレーボトルに入れて水で薄めてスタイリングウォーターとしても使うとよいでしょう。
乳液や化粧水を使った効果的なヘアケアの方法をご紹介!
ここからは、乳液や化粧水を使った効果的なヘアケアの方法をご紹介します。
乳液の効果的な使い方
効果的な乳液の使い方には以下の3つのポイントがあります。
- 乳液をつける前にブラッシング
- 乳液を手のひらで温めながらで伸ばす
- 毛先から順につける
髪に乳液をつける前に必ずやってほしいことは「ブラッシング」です。ブラッシングすることで、髪表面についたほこりや汚れを落として乳液が浸透しやすくなります。また、絡まりやすい毛先から中間⇒全体と行うことでスムーズにブラッシングできます。
乳液は手に取ったらすぐにつけずに、手のひらで温めながらまんべんなく伸ばしてください。
温めることで、髪への浸透率が上がります。また、伸ばすことで全体的にムラなくつけることができます。
つける順番は、中間から毛先に向かってつける方が多いですが、毛先がもっとも傷みやすいため毛先から順に中間⇒全体へとつけていってください。一部に偏りがないよう、全体的になじませるようにつけるのがポイントです。
髪に乳液をつける際の注意点
乳液を使ってヘアケアする際に注意したい点が3つあります。
- 一度につけ過ぎない
- アレルギー成分の有無
- 使用期限の過ぎた物は使わない
乳液はたくさんつければその分効果があるというわけではありません。一度につけ過ぎると、過剰に保湿してしまい、ベタつきや吹き出物ができる恐れがあるため、逆に不衛生になりかねません。自分の髪の長さに合った適量をみつけてつけるようにしてください。
アレルギーを持っている方は、反応する成分が含まれていないか使用前にチェックが必要です。
以前使っていた乳液の残りを使用する場合は、必ず使用期限を確認してから使うようにしてください。期限の切れた化粧品は、トラブルの原因になりやすいので注意が必要です。
効果的な化粧水の使い方
化粧水を効果的に使うためには、そのタイミングが重要です。以下のタイミングで使用することをおすすめします。
- 寝て起きたとき
- タオルドライをした後
夜にケアした髪は寝てる間に水分が失われてしまい、朝起きたときにはパサついていることもあります。そんな時は、髪に潤いを与えるために化粧水を使いましょう。
タオルドライとは、シャンプーをした後にタオルで水分を拭き取ることです。強く拭きすぎると髪を傷めてしまうので、水が滴らない程度までふき取ってください。
ドライヤーの前に化粧水をつけてあげることで、乾かした後がパサつかずにしっとりとした仕上がりになります。
髪に化粧水をつける際の注意点
化粧水はその場で水分を補うのが目的のため、時間が経てば水分が蒸発してしまいます。そのため、化粧水をつけた後は、乳液やトリートメントなどの保湿ケアが必要になることは覚えておきましょう。
肌用の化粧水は、肌を保湿することが目的の成分が配合されているため、髪につけ過ぎるとベタつくことがあります。また、ヘアカラーが色落ちしやすくなるケースもあります。
ヘアケアの代用品としておすすめの乳液・化粧水はこちら!
ヘアケアの代用品として使えるおすすめの乳液・化粧水をそれぞれ2点ずつご紹介します。
乳液:MINON(ミノン)|アミノモイスト モイストチャージミルク 100g / 定価2,200円(税込)

10種類以上の豊富なアミノ酸が配合されており、長時間潤いが持続するのが特徴です。
少し重めの使用感ですが、しっかりとした保湿感が得られます。乾燥が気になったり、お風呂上がりや寝る前のケアに最適です。
楽天で見る>>
乳液:無印良品|乳液・敏感肌用・しっとりタイプ(大容量)400ml / 定価1,480円(税込)

グリセリンなどの保湿成分が配合され、アルコールフリーのため敏感肌の方におすすめです。
無香料のためにおいが気にならず、ベタつきも少ないシンプルな使用感になります。比較的安価で400mlと大容量のため、長期間使用できるのもうれしい点です。
Amazonで見る>>
化粧水:Curel(キュレル)|頭皮保湿ローション 120ml / 定価1,300円(税込)

ベタインやグリセリンなどの保湿成分がメインで乾燥による頭皮のかゆみが気になる方におすすめです。
アルコールやメントールが配合されておらず、化粧水のようなサラッとした使用感が特徴ですが、大量に使用すると液垂れが気になるので注意が必要です。
楽天で見る>>
化粧水:Avene(アベンヌ)ウォーター 150g /定価 1,650円(税込)

天然の温泉水を使用したミネラルバランスが特徴の化粧水です。保湿に優れ刺激となる成分が配合されていないため、子供から大人まで使用できます。
スプレータイプのため、手軽に使えて摩擦感がなく、よく馴染みます。対して、部分的に少量だけ使いたい場合は調整がむずかしいです。
楽天で見る>>
Amazonで見る>>
今日からできる!お金がかからない簡単なヘアケア方法をご紹介!
さいごに、お金をかけずにきれいな髪を保つ簡単なヘアケア方法をご紹介します。今日から自宅でできる簡単な方法ですので、ぜひ実践してみてください。
シャンプーの洗い方
シャンプーは毎日行うもので、きれいな髪を保つために欠かせないヘアケアの一つです。
正しいシャンプーのやり方を4つに分けて解説します。
- 1日の汚れを浮かす「ブラッシング」
- 髪表面の汚れを落とす「予洗い」
- 頭皮の汚れを落とす「シャンプー」
- 1日の汚れを流す「すすぎ」
シャンプー前のブラッシングで髪の絡まりや1日の汚れを浮かせましょう。また、頭皮のマッサージ効果もあり、血行が良くなります。
浮かせた汚れを36~38℃のお湯で2~3分かけて予洗いを行い、髪表面の汚れを落とします。
シャンプー剤を空気と水分でよく泡立て、頭皮をマッサージするように洗っていきましょう。このとき、予洗いをしっかりとしておくことで、泡立ちがよくなりシャンプー剤の量を節約できます。
1度目のシャンプーで泡立ちがよくない場合は、すすいでからシャンプー剤の量を減らして2度洗いしても大丈夫です。
洗い終わったらすすぎになりますが、すすぎ残しがもっとも頭皮トラブルにつながる要因となります。そのため、洗う時間にかけた倍の時間をかけるイメージでしっかりすすいでください。
シャンプー後のケア
シャンプーで洗われた髪は、キューティクルが開きとても傷みやすくデリケートな状態です。濡れた髪を放置しておくと不衛生につながるため、タオルドライでしっかりと水分を拭き取りましょう。
次に、今回紹介しました乳液や化粧水を使用しても良いですし、自分に合ったトリートメントがあればそれを使って開いたキューティクルにフタをしていきます。このとき、目の粗いコームでとかすことで、髪全体にまんべんなくトリートメントを馴染ませることができます。
ドライヤーの乾かし方
長時間のドライヤーは髪にかかる負担が大きいため、できるだけ短い時間で済ませましょう。そのためには、乾かす順番が大切になります。
まず根元から乾かします。毛先は傷んでいる場合、最初に乾かしてしまうと余熱でパサついてしまうからです。また、根元の方が毛量が多く、乾くまで時間がかかるためです。
乾かす際のドライヤーのヘッドの向きも大切です。髪のキューティクルは上から下に向けてうろこ状に閉じているため、キューティクルを逆なでしないように風向きは上から下方向を意識して乾かしてください。キューティクルが閉じることで、髪にきれいな艶が出ます。
ヘアアイロンの温度と時間
ドライヤーの後に、ヘアスタイルを整えるためにヘアアイロンをする方も多いと思います。
ヘアアイロンを使う上で注意したい点は「温度」と「時間」です。
温度は150℃前後を目安に、3秒以上は同じ箇所に当てないように注意してください。髪の主成分であるケラチンはタンパク質でできており、高温によって「タンパク変性」という現象が起こり髪の毛が硬くなってしまうためです。
きれいな髪を保つ紫外線対策
髪は身体の中で最も紫外線が当たる部分とされています。
主な対策として、
・日焼け止め(スプレー、トリートメント)効果のある物を使う
・日傘や帽子
などが挙げられます。
紫外線は髪に対して「パサつき」「ハリやコシの低下」「ヘアカラーの色抜け」などの影響を与えるため、きれいな髪を保ちたい人にとって紫外線対策は必須といえるでしょう。
まとめ
乳液・化粧水を髪や頭皮につけることは、
- 髪や肌を外的要因から保護してくれる
- 乾燥の予防対策になる
- 健康な頭皮環境の促進をサポート
- トリートメント効果が期待できる
- 程よいスタイリングが可能
上記5つのメリットがあるため、問題なく使用することができます。
正しい使用方法を理解した上で、明日からのヘアケアに役立てていただけたら幸いです。
薄毛や抜け毛に悩むのは男性だけではありません。女性でも、アラフォー以降になってくると薄毛や抜け毛に悩む方が増えています。
そういった時に、「シャンプーを変えてみよう」と思われる方が多いと思います。
シャンプー売り場には、様々なキャッチコピーで薄毛や抜け毛の解決を謳ったシャンプーが並んでいますが、実はその中には、逆に症状を悪化させる可能性のある危険な商品も並んでいます。

弱り始めた「頭皮の育毛力」を更に弱めてしまうシャンプーを使い続けると、薄毛や抜け毛が悪化する危険性があります。
今回は、薄毛や抜け毛などのお悩みに適した、アラフォー女性向けシャンプーの選び方をご紹介します。
薄毛の本当の原因
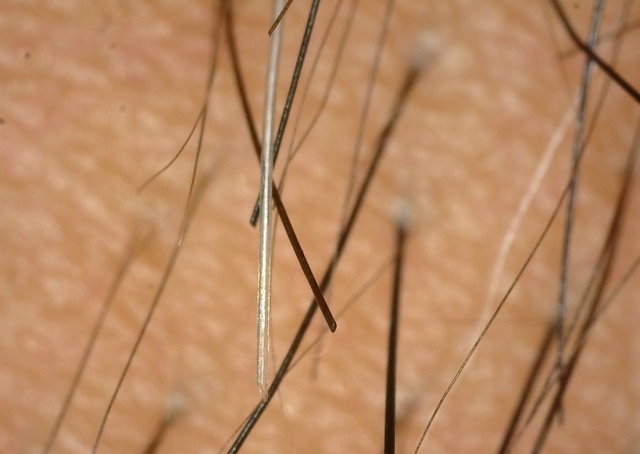
よく、「頭皮の皮脂」が薄毛や抜け毛の原因として扱われ、それをとにかく奪いさるような強力な洗浄成分を配合しているシャンプーを見かけます。強力な洗浄成分で頭を洗うと、さっぱりとした洗いあがりを実感でき、さも「薄毛の原因である皮脂を退治したぞ!!!」という満足感を得られるからでしょうか。
しかし、皮脂は髪にとって必要な存在です。頭皮にとって、天然の保護成分のようなもので、ある程度分泌されていることで、頭皮や髪を健やかに保つ働きがあります。
20代の頃と同じ感覚でシャンプーを選ぶのではなく、アラフォー女性は、洗浄力がマイルドなシャンプーを選びましょう。
自分に合ったシャンプーの見極め方

それでは、どうやってご自分に適したシャンプーを見分ければよいのでしょうか。
大切なことは、CMやパッケージだけで判断しないことです。頭皮や髪には個人差があるので、有名なシャンプーがあなたにとってのベスト・シャンプーというわけではありません。製品の裏側にある成分一覧を確認して客観的に判断しましょう。
シャンプーの成分表

裏面の成分一覧は、配合量の多い順に掲載する決まりになっていますので、一番上から5番目~10番目位までを確認してみると良いでしょう。シャンプーにはかなり多くの成分が配合されているケースが多く、全ての配合成分を確認するのは難しいからです。
シャンプーの分類

シャンプーは、以下にご紹介するように何種類かのタイプに分類することができます。メインで配合されている成分から、どのタイプのシャンプーなのか判別しましょう。
シャンプーには、汚れを洗い流すための洗浄成分(界面活性剤)が入っていますが、その種類によって大きく分類することができます。
代表的なものとしては、高級アルコール系、石鹸系、アミノ酸系、ベタイン系などがあり、各々メリットとデメリットがあります。
1 高級アルコール系シャンプー
中でも、「高級アルコール系」と言われる洗浄成分の入ったシャンプーは、洗浄力が強いのが特徴です。
泡立ちが良く、材料が安価なため、お手ごろな値段のシャンプーとしてスーパーやドラッグストアに多く並んでいますが、皮脂の分泌が少なくなってきた女性にはおすすめできません。
高級アルコール系の洗浄成分とは、ラウレス硫酸ナトリウム・ラウリル硫酸ナトリウム・ラウリル硫酸アンモニウム・スルホン酸ナトリウムなどのことを指します。
2 石鹸系シャンプー
石鹸系シャンプーは、「石鹸」のイメージから体に優しいものと思われがちですが、基本的に洗浄力は強いです。
また、髪は本来弱酸性なのに対し、石鹸系シャンプーはアルカリ性で、ダメージを受けやすい状態にしてしまいます。
3 アミノ酸系シャンプー、ベタイン系シャンプー
数あるシャンプー類でも、洗浄力が比較的マイルドと言われているのが、アミノ酸系やベタイン系のシャンプーです。
具体的には、ラウロイルメチルアラニンNaや、ココイルグルタミン酸Na、コカミドプロピルベタイン、ラウラミドプロピルベタインなどが配合されていることが多いです。
洗浄力がマイルドで低刺激なため、必要な皮脂まで取り除いてしまうことがなく、頭皮を乾燥させる心配がありません。
ただ、泡立ちが悪いため、「すっきり洗い流した!」という爽快感には欠けることがあります。でも、健やかな頭皮を守るためですので、慣れてしまいましょう。
また、材料が比較的高いため、商品としても高価なものが多いようです。あまりスーパーやドラッグストアでは販売されておらず、美容院の専売品として、もしくはインターネット通販などで売られているのを見かけます。ここは、一生をともにする自分の髪のために、シャンプーへ投資してみてはいかがでしょうか。
使用感の判断について

シャンプーの使用感は、毛髪のコンディションだけで判断されがちですが、健やかな髪を育てるためには、頭皮のコンディションもとても大切です。
髪がいくらサラサラでも、頭皮が乾燥してカサカサな状態では、これから先、丈夫で健康な髪を育み続けることができません。
シャンプーによる毛髪のコンディションの変化は比較的すぐに分かりますが、頭皮のコンディションは時間をかけて変わります。頭皮のチェックポイントは、かゆみや赤みがでないか、程よい皮脂が保たれているか(カサカサすぎず、ベトつきすぎない)です。
特に皮脂の分泌量はすぐには変わらないので、判断に時間がかかります。
しばらくすると頭皮がシャンプーに慣れ、皮脂の分泌量がおさまってきますので、様子を見る必要があります。
そのため、シャンプーとの相性はしばらく使用してから判断しましょう。異常が生じない限り、最低でも2~3週間は使ってみることをおすすめします。
どのようなシャンプーを選ぶかは、アラフォー以降に健やかな美髪を保つために、とても重要な問題です。ご家族で同じものを使っている、という方が多いと思いますが、できればその年齢や性別、生活環境に適したものを個々に選ぶのが理想的です。
髪は見た目の印象の8割を決めると言います。これから先、薄毛や抜け毛に悩まないためにも、早めにシャンプーの見直しを始めて、ご自分に適したものを見つけられると良いですね。
美容をアップデートするサイトコスメ部では「髪の毛を乾かさないメリット・デメリット」が詳しく紹介されていますので、こちらも参考にしてください。
髪の毛のケア、どんなことを意識していますか??
こんにちは。インナービューティープランナーの有光眞織です。
季節が夏に近づくにつれて、気になるのが紫外線。お肌のケアを入念にする方も多いと思います。しかし、髪の毛についてはあまり意識せず、『いつも通りのヘアケア』で済ませてしまう方も少なくありません。
紫外線で髪がパサパサになったり、色あせてしまうと、印象が大きく変わります。
今回は、体の内側から、ツヤ髪を作る方法をご紹介します。
髪が傷んでしまう意外な原因

髪の毛は、主にケラチンというたんぱく質、脂肪、ミネラルによって構成されています。一般的には、髪が傷む原因として、紫外線や乾燥、間違ったシャンプーやヘアアイロンの使用などが挙げられます。
しかし、それ以外にも実は『体内の糖化』が原因の1つだということは、意外と知られていません。
『糖化』とは、老化要因の1つです。体内のたんぱく質が、過剰に摂取された糖質と結びつき、体温で加熱されたり紫外線を受けたりすることによって、『AGE』と呼ばれる最終糖化産物に変化してしまうものです。よく言われる『酸化』が体のサビだとすると、糖化は体のコゲとも呼ばれます。この現象は、年齢を重ねるほど体内に蓄積されていき、肌のしわやしみ、血管の硬化などに悪影響もたらします。
例に漏れず髪の毛もケラチンのAGE化によって、弾力が失われて傷みやすくなるだけでなく、抜け毛や白髪の原因にもなるのです。
それでは、この『糖化』を回避するには、どうしたら良いでしょうか。
ヘアートリートメント的な食習慣-3ポイント

髪の毛に良い食べ物として、ワカメなどの海藻類を思い浮かべる方もいらっしゃると思います。しかしそれ以外にも、糖化を回避し、ツヤ髪を生み出す食習慣はあります。
1.AGEリッチな食材を避ける
例えば、水炊きの鶏肉に対して、フライパンで焼いた場合のAGEは約5倍。そして唐揚げにした場合には10倍にもなります。AGEは、糖質とたんぱく質を含む食材の加熱温度が高く、加熱時間が長ければ長いほど発生するため、このようなAGE値の違いが現れるのです。
AGEの数値が高い調理方法としては、『揚げる>焼く>煮る>蒸す>生』という順番になるため、こんがりとした焼き色がついた焼きプリンより、普通のプリンを選ぶなど、加熱の製造工程を極力含まない食材選びをするのがコツの1つです。
2.血糖値を急上昇させない食べ方
AGEは、血糖値の高い状態が長ければ長いほど発生するといわれています。そのため、普段のお食事の際に、いかに血糖値をコントロールするかが重要です。
■食事
糖質を多く含むものを控えることがまず提案されますが、せっかくのお食事やスイーツを我慢するのも辛いですよね。そんな時には、水溶性食物繊維を多く含む海藻類やお野菜を炭水化物より先に食べること(いわゆる、ベジタブルファースト)を心がけると良いでしょう。

糖化の原因である糖質の吸収を抑えることができます。また、糖質のエネルギー代謝に欠かせないビタミンB1(非精製食品や大豆製品、ぬか漬けやキノコ類など)を一緒に摂るのもオススメです。
■生活習慣
背筋を伸ばし良く噛んで、丁寧に時間をかけて食べることで、同じものを食べても血糖値はゆるやかに上昇します。ながら食べをせず味わって頂くことで、満足度も高まり食べすぎを防げるため、結果として糖質の過剰摂取も抑えることができます。
3.ビタミン・ミネラルの補給

ビタミン・ミネラルの補給で、糖化対策&ツヤ髪作りのW効果を狙いましょう。
■ビオチン
健康的な髪の毛を育むには、ビタミンやミネラルが重要な役割を担います。ビタミンは、全部で13種類ありますが、中でも『ビオチン』は、糖質の代謝だけでなく、白髪や抜け毛対策に効果があります、これは、落花生や大豆製品、くるみ、キノコ類に豊富に含まれています。
■亜鉛
また、ミネラルはタンパク質や脂質と共に体を作る栄養素で、全部で16種類あります。中でも、新陳代謝を促進しケラチンの合成に働く『亜鉛』は、糖の代謝にかかわるインスリン合成にも一役買う優れもの。亜鉛といえば牡蠣が有名ですが、高野豆腐や豚や牛のレバー、納豆などにも含まれます。
食生活を整えて、内面から輝きましょう!
食生活の改善は、サロンでのプロの手によるトリートメントのような即効性はありませんが、今から日常的な対策をすることで、髪の毛も肌も質感は確実に変化していきます。
私たちは生きていく以上、『老化しない』ということは難しいですが、納得と満足のゆく年齢を重ねていく工夫をすることはできます。ぜひ、今日のお食事からお試しください。
参考サイト:AGE測定推進協会
参考文献:あたらしい栄養事典(日本文芸社)




