睡眠不足や食生活の乱れなどから疲れが溜まると、体にだるさを感じやすくなります。
ここでは、だるさの原因や、疲労回復に効果的な栄養素、コンビニで買えるだるさ対策の飲み物、疲労回復レシピや生活習慣などをご紹介します。
血の巡りに注目!?身体がだるい原因ってなに?
体のだるさの原因はいろいろありますが、その一つに「血の巡り」が関係していると言われています。
食べ物は、消化吸収され最終的に血液を通じて体の全身に巡りエネルギーとなります。血液には、体に必要な酸素や栄養素などと一緒に、老廃物や二酸化炭素も運ばれ外に出す働きもあります。
さらに、疲労物質の乳酸などがたまると、血の巡りも悪くなります。
血の巡りが悪くなると、全身に十分な酸素や栄養素が供給されず、さらに老廃物も溜まるため、体のだるさに繋がるのです。
その他、だるさの原因には、血圧が関係している場合もあります。
血を巡らせるポンプの働きをするのが心臓ですが、心臓の圧力(血圧)が低下したり、自律神経のバランスを崩すと、体のだるさを感じやすくなります。血圧が低いこと自体は問題ではないのですが、血圧が低くなった状態からくる「だるさ」を感じる方は、日頃の生活習慣を見直し改善していきましょう。
さらに、貧血がだるさを感じている原因の場合もあります。
顔色が悪く疲れやすい慢性的な「だるさ」を感じるタイプは、血液中の赤血球の量が関係している可能性があります。血液中のヘモグロビンが少なくなったり、薄くなったりして貧血状態の時は、鉄分やたんぱく質の入った飲み物で予防をしていきましょう。
血の巡りが悪くなると、体のすみずみまで栄養素が行き届かなくなり、体に老廃物がたまりやすく疲労が蓄積します。日頃から血の巡りを良くする食生活や運動を意識していきましょう。
プロ直伝!疲労回復に効果的な栄養素とは
疲労回復に必要な栄養素のひとつに、エネルギー代謝をあげる「クエン酸」があげられます。他にも代謝を助ける「ビタミン類」や体を構成する「アミノ酸」などの栄養素も関係しています。その役割を理解して上手に取り入れていきましょう。
酸っぱさが決め手!疲れを瞬間的に解消するクエン酸

運動や汗をかいたりした後に、体が疲れて「だるさ」を感じ、酸っぱい飲み物が欲しくなることはありませんか?
このような「だるさ」を感じた時に、自然と酸味のあるドリンクを飲みたくなるのはのは、体がクエン酸を欲している証拠です。クエン酸は、レモンやグレープフルーツなどの柑橘類、梅干しに多く含まれています。
このクエン酸は、体が代謝してエネルギーを作り出す「クエン酸回路」の中で、重要な役割を果たしています。クエン酸があると、体の代謝が活発に行われ、エネルギーを作り出しやすくなるのです。エネルギーが足りないと感じる「だるさ」には、クエン酸を補給することが鍵となります。
他にもクエン酸は、ミネラルを吸収させたり「抗酸化作用」と呼ばれる体を酸化しづらくして老化を防いだりする役割もあります。
ビタミンB群で疲れ知らずの体に
疲れがたまって肌荒れや口内炎になることはありませんか?
肌荒れや口内炎などができてしまう原因の疲れには、ビタミンB群の補給をおすすめします。ビタミンBは、いくつかありますがどれも代謝を助ける役割があります。
B1は糖質の代謝、B2は発育促進、B12は神経の機能とそれぞれに働きかけます。中でもB6は、体を構成しているタンパク質が、小さく消化されてできた「アミノ酸」の代謝に関わっています。そのためビタミンB6が不足すると体の疲れがでやすくなります。
これらのビタミンを1日の十分な量を食事から満たすのは難しい場合は、各種ビタミンの含まれた市販のドリンクやサプリメントを上手に利用していきましょう。
男女別!女性・男性それぞれに合った体に良い飲み物は?
男性と女性に合ったおススメの飲み物をそれぞれご紹介します。
男性向けのおススメの飲み物
疲れた体には、仕事の合間にすっきりと飲めてすぐに力の出る「炭酸系のエナジードリンク」がおススメです。
男性は、食事で不足しがちな食物繊維とビタミンを補える緑黄色野菜を多く使ったスムージーもよいでしょう。特に朝食を抜きがちな方は、素早くエネルギーに変わるバナナを使ったものや、タンパク質を補える豆乳もおすすめです。
脂っこい食生活が中心となっている方は、コレステロールや中性脂肪を下げる効果が期待できる「お酢」の含まれたソーダなどで疲れをとっていきましょう。
女性向けのおススメの飲み物
女性はホルモンバランスの変化も多く、冷えなどに悩まされることもあるため、体を温める白湯、生姜やそば茶などがよいでしょう。むくみやすい方は、利尿作用のあるハーブティーなどもおススメです。
女性は生理や出産などから、カルシウムや鉄分の不足が気になります。朝の目覚めが悪い時には、鉄分の構成に必要なタンパク質とカルシウムを補える牛乳や豆乳、ヨーグルトドリンクなどを使ったスムージーで造血のサポートをしていきましょう。
即効性◎スーパーやコンビニで買える市販の”だるさ解消栄養ドリンク”5選

すぐに「だるさ」を解消したい時に便利なのが、コンビニで買える市販のドリンクです。疲労回復ドリンクに迷ったら、こちらの5つはいかがでしょうか。
チョコラBBシリーズ
エーザイから販売しているチョコラBBシリーズは、種類も豊富です。女性の肌荒れに関わるコラーゲンや直接型のビタミンB2やビタミンCも豊富に含まれています。食事をするのもだるい時に、美味しくすっきりとした味わいで元気の源となる栄養素がしっかり補給できます。
C1000ビタミンレモンクエン酸
クエン酸を3000㎎含んだこのドリンクは、ビタミンD、Eも配合されているマルチビタミンな飲み物です。酸っぱい味わいに炭酸を加え、すっきり爽快感で疲れを吹き飛ばします。ハウスウェルネスフーズからのシリーズ商品です。
CCレモン
多くの人が知っているサントリーから販売のすっきりとした味わいの炭酸飲料です。飲みやすく手軽にビタミンCとクエン酸を補えます。40個分のレモンの酸味と保存料を利用しないで作った純水のドリンクは、汗をかいた時やスポーツの後にもおすすめです。
アリナミンV
仕事で忙しく連続的な体力不足を感じる「だるさ」にアリナミンVはいかがでしょうか。ビタミンB1誘導体のフルスルチアミンやビタミンB6・B12、ビタミンEもたっぷり配合されています。特に目の疲れや肩こりを伴う肉体疲労時におすすめです。アリナミン製薬から販売されています。
マルチビタミンゼリー飲料
1日に必要な12種類のビタミンを配合しているゼリー状のマルチビタミン飲料です。様々な種類の味がある中で、グレープフルーツ味はすっきりとクエン酸も摂れます。忙しくて食事からの栄養補給が難しい時、疲れすぎて食事ができない時にもゼリータイプなので気軽に飲めます。
市販で購入可能!体に良くてアレンジもできる疲労回復を助ける飲み物
コンビニで買える栄養ドリンクと合わせて、疲労回復に便利で日常的に置いておきたい栄養たっぷりなおすすめの飲み物を紹介します。
クエン酸の豊富さでは、柑橘類のオレンジジュース、レモンドリンク、グレープフルーツジュースなどがお手軽でアレンジレシピとして使えるので便利です。
お酢にもクエン酸が含まれています。お酢は、料理にも使えるので常に用意しておくといいでしょう。中でも黒酢やりんご酢は、酸味がまろやかでドリンクとしても活用できます。
さらにカルシウムやタンパク質を補うのに便利な飲み物に、牛乳、豆乳、ヨーグルトがあります。最近ではハリウッドセレブの間で、アーモンドミルクやオーツミルクなども好まれています。
最後に、ハーブやスパイス類はおうちでアレンジドリンクを作る際に役立ちます。中でも、シナモン、陳皮などの体を温めるタイプのものは、常備しておくとよいでしょう。血の巡りをよくし体を温めます。むくみやだるさには、カモミールなどの利尿作用があるものがおすすめです。
誰でも作れる”疲労回復ドリンク”レシピを5選紹介
上記でご紹介したドリンクや、ハーブ、スパイスを組み合わせた、疲労回復におススメのお手軽なレシピをご紹介します。
レモン入りジャスミンティー
レモンの酸味とジャスミンの香りがリラックス効果をもちながら、血の巡りをよくし、だるさを解消します。女性の冷え性の予防にも効果が期待できます。
○材料(1人分)
ジャスミン茶葉・・・小さじ2
レモンの輪切り・・・1枚
はちみつ・・・お好みで
○作り方
ポットにジャスミンの葉入れ湯を注ぐ、
5分置いたらカップにそそぎレモンの輪切りをのせる
お好みで、はちみつを入れて甘味をプラス
グレープアーモンドスムージー
即効性のエネルギーアップに役立つぶどう糖とアーモンドミルクでタンパク質の補給ができます。食欲のない朝にピッタリです。スムージーでもミキサーがなくてできるのでおすすめです。
○材料(1人分)
ぶどうジュース・・・100㏄
アーモンドミルク・・・60㏄
チアシード・・・小さじ1
アサイーパウダー・・・小さじ1
氷・・・適量
○作り方
全ての材料をタンブラーに入れる
蓋をしてよくシェイクする
そのまま飲んでもグラスに注いでも
梅干黒酢ソーダー
クエン酸の効果を期待できる黒酢と梅干しを使ったソーダです。二日酔いでだるい日にもぴったりの飲み物です。
○材料(1人分)
黒酢・・・大さじ3
つぶした梅干・・・1個
はちみつ・・・大さじ3
炭酸水・・・180㏄
氷・・・適量
○作り方
グラスに黒酢と梅干、はちみつを入れてよく混ぜる。
氷を入れ炭酸水を加える
タンブラーでよく混ぜる
ホットジンジャーラテ
生姜で体を温めながら、タンパク質の補給とリラックス効果のあるスパイスで1日の疲れを癒してはいかがでしょうか。寝る前におすすめです。
○材料(1人分)
牛乳または豆乳・・・200㏄
すりおろした生姜・・・大さじ1
てんさい糖・・・お好みで
シナモン、カルダモン・・・少々
○作り方
全ての材料を鍋に入れて沸騰するまで温める
ひと煮立ちしたらカップに注ぐ
柑橘カムカムミックスドリンク
数種類のお好みの柑橘類を絞って、柑橘類の中でビタミンC量が最強と言われるスーパーフードのカムカムパウダーを刻んだミントと一緒に合わせます。爽やかな風味と豊富なクエン酸でだるさ解消に効果的です。
○材料(1人分)
グレープフルーツ果汁・・・100㏄
レモン果汁・・・小さじ2
みかん果汁・・・100㏄
カムカムパウダー・・・小さじ2
ミントの葉・・・5枚
○作り方
柑橘類が生の場合は絞り機で果汁をとってボールに入れる
ミントの葉は、みじん切りにする
全ての材料を泡立て器でよく混ぜグラスに注ぐ
栄養ドリンクだけではNG?疲労回復に欠かせない3つの習慣

栄養ドリンクを利用しながらパワーを補給する即効性の疲労回復法もありますが、基本は「睡眠」「入浴」「食事」の3本柱で規則正しい日頃の生活習慣を送ることが大切です。
しっかりとした睡眠
疲れの元を無くすには、体の休養となる睡眠が大切です。夜更かしをしないで、しっかりと睡眠時間を確保できる生活をしましょう。人は暗くなるとメラトニンと呼ばれる睡眠ホルモンで安眠を誘い、朝目覚めると日の光でメラトニンからセロトニンというホルモンに変わります。そのため、睡眠前に携帯の光などを浴び続けると、セロトニンからメラトニンに切り替わるスイッチが上手くいかず、睡眠の質を低下させ目覚めが悪くなります。
眠りが浅いと感じる時は、就寝前に携帯やパソコンの明かりにあたりすぎていないか見直しましょう。寝る前の過剰な光は睡眠の質を低下させます。
体を温める入浴
むくみや冷えは、体の血行の悪さから生じます。寝る前に、ぬるめのお風呂にゆっくりとつかり、1日の体の疲れをとりましょう。夜寝る前の入浴は半身浴などを利用して、体全体を温めます。
また朝の目覚めをすっきりしたい時は、十分な水分補給をした上で、ぬるめのお湯から熱いお湯に切り替えることで、副交感神経から交感神経が目覚め、体も目覚めます。
目的に合った入浴方法でだるさを解消しましょう。
偏りのない食生活
無理なダイエットや不規則な生活が続くと、食生活にも偏りができてしまいます。食事は体作りの基本です。自分の体に必要な栄養素をしっかりサポートする食生活を送りましょう。
エネルギーの源となる炭水化物、体の構成に必要なタンパク質を中心に、野菜や果物からビタミン・ミネラルを十分に補っていきます。
朝食を抜いたり、寝る直前の食事などはできるだけ避け、栄養ドリンクなどを上手に取り入れながら体の芯からパワーを作っていきましょう。
こんにちは。看護師のアロマ&ハーブスクールkaorino coccoleの植野香織です
この時期になると手足が冷えて良く眠れない、トイレによく行くようになった、肩や腰が痛い、重たい生理痛などに悩む相談が多くなります。
靴下を履いて寝る、水分を控える、鎮痛剤を飲むなど一つの不調にとらわれ対処しがちですが、ちょっと待って!
その不調は身体の冷えが原因かもしれません。
今回は、看護師が伝える癒しの冷え予防をお伝えします。
〝冷え″を軽く見ないで!

根本的な原因となっている冷えを改善しないと免疫力が下がり身体がだるい、腰痛や肩こり、月経不順、風邪にかかりやすいなど複数の不調や様々な病気につながる恐れがあります。
自律神経や女性ホルモンバランスの乱れから血液循環が悪くなることで女性は特に冷え性になりやすく、毎日の仕事や家事、子育てに追われる女性は自分の身体のケアにまでなかなか時間を持てないでいるのではないでしょうか?そんな女性のために手軽にできるケアを紹介します
血流をよくする食事を採る

・ブロッコリースプラウト
ブロッコリースプラウトとは発芽してすぐのブロッコリーの幼い芽のことです。
ブロッコリーよりも栄養価が高くスーパーで150円位で購入できます。
血行を良くするβ―カロテン、ビタミンEが豊富に含まれストレスやお肌に良いとされるビタミンCが入っています。加熱すると酵素が壊れてしまうのでサラダや酢の物にして食べます。付け合せとして摂取できるので手軽に取り入れる事ができますね。
・生姜
冷えをよくする食事というとすぐに生姜が浮かぶ人が多いかもしれませんね。生姜に含まれるジンゲロールが血流をよくして代謝をアップしてくれます。スープや味噌汁に味付けとして入れたり、臭み取りにお魚の煮付けに入れたりすると手軽に摂取できます。生姜湯や生姜を乾燥させたジンジャーハーブティーも香り良く美味しいです
・納豆
納豆に含まれるナットウキナーゼは血液をさらさらにしてくれます。ただし心疾患や脳疾患などの治療にワーファリンという抗凝固剤を飲んでいる方は腸内でビタミンKが合成され、ワーファリンの効果を弱めてしまうため納豆は控えてください。
身体を温め血行を促すアロマテラピー

アロマテラピーとは
植物の香りは心地よく、脳にある自律神経系、内分泌系、免疫系などのバランスを補う視床下部に伝わることにより心や身体に働きかける力があります。
アロマテラピーでは植物の香りとして精油(エッセンシャルオイル)を用います。
精油(エッセンシャルオイル)とは
植物の花、葉、果皮、果実、心材、根、種子、樹皮、樹脂などから抽出した天然の素材で有効成分を高濃度に合有した揮発性の芳香物質です。
一番は心地よいと思う香りを取り入れていく事が大切!その次におススメのアロマを紹介します
身体を温め血行を促す成分を持つアロマ
・スイートオレンジ
オレンジの皮を圧搾して抽出されます。柑橘系のフレッシュな香りはリラックスとリフレッシュを与え心と身体両方への加湿効果があり、冷えや風邪による不調を緩和してくれます。
・スイートマージョラム
シソ科でハーブ系の香りは心を温めリラックス効果があります。血液の流れを良くするので冷え、腰痛などを緩和してくれます。また、血管を広げて血圧を下げたり、消化器の不調改善に役立ちます。
・ジュニパーベリー
ヒノキ科で樹木系の香りは洋酒のジンの香り付けに用いられてきました。利尿や発汗などを促すデトックス効果があり、新陳代謝を促進し、身体の機能を活発にして浄化し温め整えてくれます。授乳中で排尿が滞っている人の母乳過多のバランスをとるなどにも役立ちます
日常生活への活用方法・レシピ

・トリートメントオイルで全身ケア
お風呂に入った後、寝る前にホホバオイルやスイートアーモンドなどの植物油30mlに精油5滴混ぜて手や足、身体に塗布しトリートメントします。
・アロマバス、バスフィズ
精油を直接お風呂に入れる場合は200ℓの浴槽に対し5滴以内で垂らします。精油はお湯に溶けないのでよくかき混ぜて入浴しましょう。
重曹とクエン酸の組み合わせで作る入浴剤もおススメです。お風呂に入れると発生する炭酸ガスが血行を促進させてくれます。ビニール袋を準備し、その中に重曹大さじ4入れ精油を5滴以内、クエン酸を大さじ1強入れよく混ぜたら完成です。湯あかを取ってくれるので残り湯でのお風呂掃除も楽です。
冷えは万病の元

これからの季節を快適に過ごす為には様々な不調、病気に繋がる冷えに血行を促す食事、運動を取り入れ心地よい香りに癒されながらケアする事です。また、アロマテラピーを寝る前に活用する事で質の高い睡眠を得ることができます。
このように、日常生活を整えていく事で免疫力が上がりストレスや冷えに負けない身体を得ることが出来るのです。ただでさえ仕事に家事に子育てに毎日忙しい女性へ、その大切な心と身体に癒しを。
寒い季節になり、身体の冷えを感じている方も多いのではないでしょうか。
手足などの末端部分が冷たい、上半身がのぼせる、顔が火照るなどの色々な症状をお持ちの方もいらっしゃると思います。
最近では、季節関係なくお身体の冷えを訴えるお客様もサロンには沢山いらっしゃいます。冬は外気の寒さ、夏は冷房などによる室温の寒さ・・・
しかし、皆さんが今感じられている冷えは外気や冷房の寒さからだけでしょうか?
冷えの原因には寒さだけではなく色々な原因があります。その中には、女性ホルモンが原因と考えうるものもあります。
私は女性ホルモンケアができるアロマテラピースクールとサロンをしています。多くの女性が冷えを感じていらっしゃいますが、その原因が分かっている方は多くはいません。
今回は女性ホルモンと冷えの関係についてご紹介します。
女性ホルモンについて
女性ホルモンは脳の視床下部から下垂体へ伝達、そこから卵巣に伝わり、卵巣から分泌される化学物質です。
その卵巣から分泌されるホルモン「卵胞ホルモン(エストロゲン)」と「黄体ホルモン(プロゲステロン)」の2種類が女性ホルモンの正体です。
この2つのホルモンが順調な方ですと約28日周期のリズムで卵巣から分泌されて、排卵や月経を生じさせます。
女性ホルモンの役割
1 卵胞ホルモン(エストロゲン)・・・女性らしさのホルモン
- 妊娠に備えて子宮内膜を厚くする
- 受精卵の着床を助ける
- 女性らしい体つきを作る
- 新陳代謝を促す
- コレステロール値を下げる
- 骨、関節、筋肉、血管などを丈夫にする。
- 内臓脂肪をつきにくくする
- 肌にハリやツヤを持たせる
- 髪に艶やかに保つ
- 脳や自律神経の働きをよくする
- 記憶力を上げる
- 胃腸の働きをよくする
- 気分を安定させる
まさに美のホルモンです。
2 黄体ホルモン(プロゲステロン)・・・妊娠のためホルモン
- 子宮内膜を受精卵が着床しやすい状態に整える
- 妊娠したのち、妊娠を継続させる
- 子宮内膜を更に厚くする
- 卵胞の発育を抑制する
- エストロゲンの作用を抑制する
- 体温を上昇させる
- 水分を溜め込む
- 新陳代謝を遅らせる
- 皮脂分泌が活発になる
妊娠を維持させる、母になるためのホルモンです。
2つの女性ホルモンには一例ですが、上記のような働きがあります。
月経後~排卵前はエストロゲン、排卵後~月経までプロゲステロンが優位になり、バランスを保っています。
冷えと女性ホルモンの関係
女性ホルモンの1つである「黄体ホルモン(プロゲステロン)」には体温を上昇させる働きがあります。
プロゲステロンは排卵後から月経期に分泌量が増えて優位になるホルモンです。
プロゲステロンが多く分泌される時期というのは受精卵を着床させ、妊娠を維持するためにひと月の中でも一番体温が上昇します。
プロゲステロンが多く分泌されている時期は、エストロゲンが優位な時期よりも体温が約0.5℃高い状態になります。
2つの女性ホルモンが分泌される卵巣が何かしらの原因(寝不足、ストレス、加齢など)で機能が低下して正常に分泌出来ないと、司令部である視床下部にも影響を与えてしまい、自律神経の乱れが生じます。
自律神経は血管の収縮、拡張も司っているので、その乱れは「冷え」の原因となりうるのです。
「冷え」改善の対策
1 身体を温める食事を積極的に摂取する
- 香りの強い野菜「ネギ」「ショウガ」「ニンニク」「ニラ」「根菜類」は冷え性改善に力を発揮します。
- ビタミンB1「豚肉」「卵」「大豆類」は摂取エネルギーを燃やして熱に変えてくれます。
- ビタミンC「緑黄色野菜」「果物」等は貧血の予防、毛細血管を強くする働きがあります。
- ビタミンE「ウナギ」「アーモンド」等は血行を良くします。
- たんぱく質「魚」「肉」「大豆製品」等は熱エネルギーとなります。
*食べ物から摂取が難しいようでしたら、サプリなどで補うこともおすすめです。
2 運動を心がける
血行を促す上で効果的なものと言えば、「運動」です。
ウォーキングやヨガ、ストレッチなどゆっくりと筋肉を動かすようなものがおすすめです。
筋肉の伸び縮みで熱を消費、血管の収縮で血流もよくなり、身体もポカポカしてきます。
3 アロマテラピーの力を借りる
冷えや血液循環、女性ホルモンの働きを整えるエッセンシャルオイルをブレンドして日頃の生活に使用してみましょう。
- 冷えを改善する…「ジンジャー」「ブラックペッパー」「ユーカリ」
- 血液循環を良くする…」「ジュニパー」「サイプレス」「ローズマリー」「ペパーミント」など
- 女性ホルモンを整える…「ゼラニウム」「クラリセージ」「ローズ」など
使用方法
1 アロマバス

バスタブにお湯をはり、お好きな香りの精油を3~5滴いれてよく混ぜます。
精油を垂らしたバスソルトやバスボムなどもおすすめです。
2 フット・ハンドバス

洗面器に少し熱めのお湯を張りお好きな香りの精油を1~3滴入れてよく混ぜます。
4 アロマトリートメント
ホホバオイルなどのベースオイル10mlに精油2滴を入れて、よく混ぜます。
入浴後にお腹のセルフトリートメントがお勧めです。
精油は一例です。
ご使用中にお肌に違和感がございましたら、すぐに洗い流し、それでも違和感が残りましたら、医師にご相談下さい。
女性特有の疾患をお持ちでホルモン療法をお受けの方は治療に影響のあるものもありますので、専門家にご相談してからご使用ください
冷え性と女性ホルモンの関係と、冷えの解消法をお伝えいたしました。
冷えには女性ホルモンや自律神経だけではなく色々な要因があり、大きな病気が隠れている場合もあります。
気になる方は病院に受診することをお勧めします。
こんにちは。 健康美容家の櫻井啓子です。
日に日に寒さが厳しくなって来ますね!
皆さんは、『冷え』を感じる事はありますか?
外気が冷たくなってくると、手足が冷えることがありますよね。
ただ、これは人間の生理的反応なので仕方のないことなのですが、、、
- 室内にいるのに手足が『冷え』ている。
- 周りの人は何でもないのに、自分だけが、『冷え』ている
- いくら暖めても『冷え』が取れない。
このような症状が一つでも当てはまる方は、注意が必要です!
また、こういった『冷え』に、本人が気付いていない場合もあるのです。
この『冷え』をそのままにしておくと、何らかの不調に繋がり、放っておくと大きな病気へとなりかねません!
最近は、『二人に一人がガンになる時代』、とも言われていますが、実は、『冷え』とガンにも密接な関係があるのです。
冷えが引き起こす症状

・入眠障害
夜、ベットに入ってもなかなか眠れない、という事がありませんか?
それは『冷え』ているサインです。
通常、寝ているときは、体温は低くなるもので、手先や足先などから熱を放出し、体の中心部の体温を低下させます。しかし、手足が冷たくなっていると、なかなか熱を逃す事が出来ず、体温調節が上手くいかずに『眠れない』という状態になっています。
・肌荒れ
皮膚が冷えていると、表面付近の毛細血管の血行が悪くなります。そうすると、血液を通しておこなう細胞内の不要な老廃物の回収や、酸素や栄養素の吸収が悪くなってしまい、乾燥してしまったり肌荒れを起こしたりします。
また、ターンオーバーのサイクルにも影響が出て、古い角質が残ってしまったり、毛穴に皮脂が詰まったりして、吹き出物や肌荒れ、シミ、シワの原因ともなります。
・肥満・むくみ
痩せにくいとか、浮腫みやすいと感じている方も、『冷え』の積み重ねが原因の場合があります。
身体が冷えてくると、ホルモンの分泌や代謝がうまく出来ないことから、皮下脂肪が溜まりやすくなり、肥満に繋がります。また血行が悪いことからも、老廃物や水分が溜まってしまい、むくみに繋がるという状態です。
・低体温
『冷え』は放っておくと、表面だけの『冷え』から、体の中心部まで『冷え』て、平熱が下がり、低体温となっていきます。
人間の体は、体温が高い方が免疫力が上がります。
風邪をひいた時に高熱になるのは、熱を上げて免疫力を高めて、ウイルスと戦う為なのです。
逆に、がん細胞は低体温時の方が活発に活動できます。即ち低体温の方が、がん細胞にとっては住みやすい環境なのです。
低体温=ガンではありませんが、実にガン患者の半数以上が低体温だったというデータも出ているそうです。
『冷え』の原因は?

ストレス
日々、知らないうちにストレスを溜め込んでいませんか?
一見、何の関係もなさそうですが、実はストレスと『冷え』は、密接に関係しています。
ストレスがかかると、脳が交感神経を活発にして興奮状態にします。この状態が続いてしまうと、神経が休まる事がなく疲れ果ててしまい、自律神経が乱れてきてしまうのです。体温調節は自律神経が司っているので、ストレスを溜め込んでしまうと、体温調節が上手くいかず、『冷え』の状態に陥ってしまいます。
ホルモンの乱れ
女性は特に生理の期間や更年期になってくると、ホルモンバランスが乱れやすくなります。ホルモンのバランスが崩れると、自律神経にも影響が出てきます。よって体温調節にも狂いが出て、『冷え』の状態になっていきます。
最近は男性にも『冷え』を感じている人が多いようですが、男性の場合は殆どの方はホルモンが原因ではなく、ストレスや食生活、運動不足による『冷え』が多いようです。
食生活
偏った食生活になっていませんか?お肉や加工食品などが増えて、糖質や脂質の摂取が増えてしまい、野菜や果物から摂れる、ビタミン、ミネラル、食物繊維が不足してしまうと、血液がドロドロになり、動脈硬化を招きます。動脈硬化は血管が狭くなり、血流も悪くなってしまうため、『冷え』が生じてきます。
冷え対策
寝つきが悪い方向けの対策
夜、なかなか寝付けない方は、就寝前に湯船で半身浴などして身体を十分に暖めたり、暖め効果のあるハーブティーなど※を飲むと良いでしょう。
※カモミールや ヤロウ、シナモン、ドライジンジャー、エルダーフラワーなど、またはこれらが配合されたものがおすすめ
乾燥肌の対策
また、肌の乾燥が気になったら、お風呂で蒸しタオルをするのもよいでしょう。
『熱いお湯』と『冷たい水』を用意し、タオルを浸して固く絞り、交互にお顔に載せるのを繰り返します。お肌の新陳代謝が活発になりますので、血行が良くなります。
気付いた時に温めた手で顔を覆い、軽く上下左右にマッサージするだけでも良いでしょう。
痩せにくい人の対策
痩せにくいと感じている人は、代謝をあげる事が重要です。運動不足になっていませんか?
熱を生み出せるのは筋肉です。バスや電車の一区間を歩いてみたり、普段使用していたエスカレーターやエレベーターを階段にするなどして運動量を増やし、筋肉をつけて代謝UPを目指しましょう。
皆さん、いかがでしたか?
前述のように『冷え』には、ストレスや食生活などの生活習慣がとても影響しています。
ストレスを感じたら、誰かに話を聞いてもらったり、何かでその都度発散したりすることが大切です。
30分歩くと自律神経が整ってくる、というデータもあるそうです。運動不足解消のためにも、軽い散歩程度に歩くのも良いですね。
また、睡眠不足は気づかぬストレスとして身体に負荷がかかっています。なるべく十分な睡眠や休息がとれるよう、心がけていきたいですね。
出来るところから少しずつ!
今年の冬は、『冷え』知らずで過ごしていきたいですね。
「私、冷え体質なんです…」
こんにちは。管理栄養士の 豊永彩子です。
このように、日頃から多くのお客様から、「冷え体質」という悩みを聞きます。
「体質」と思い込んでいるその「冷え」は、本当に変えられないのでしょうか?
確かに、体質もあるかもしれませんが、実は、当たり前になっている “習慣”を少しずつ変えていく事で、「冷え」やそれにともなう「不調」を改善することはできます。
「冷え」などの “病院へ行くほどではない不調” は「不定愁訴-ふていしゅうそ-」と呼ばれていますが、これは身体からのサインです。このようなサインを見逃さずにケアする事で、今既に抱えている不調の改善や、全身の健康と美しさに繋がります。
「冷え」はあらゆる不調を連れてくる
「冷え」を訴える女性は、冷えがない女性と比べ、疲れと睡眠不足を感じています。(女性の冷えと睡眠に関する調査2018※)
冷えはあらゆる不調を招き、美しさを育む上でブレーキとなってしまう症状です。
疲れ・肌の血色低下・肩こり・腰痛・免疫力の低下・太りやすい体質…など、健康面はもちろん、仕事や日常生活の質を下げてしまう原因にもなります。
冷えをはじめとした、これらの症状の背景には、今までのあなたの習慣(食事や生活面)があります。
現在の習慣を振りかえることが 、“ 改善のヒント “になります。
※調査結果:女性の冷えと睡眠に関する調査2018 / n=1,000名(20〜50代)
https://www.yomeishu.co.jp/health/survey/pdf/20181211_hie_suimin_woman.pdf
あなたの冷え体質の原因は?
「冷え」について紐解いていきましょう。
キーワードは、3つ。 「熱を生む / 運ぶ / 保温」です。
1つ目は、熱を生めない状態が原因です。筋力の低下や食事量や内容に課題のあります。
2つ目は、熱を身体に届けるシステムを担う、自律神経の乱れが原因です。
3つ目は、トイレの回数が自然に減ってしまったりと、デトックス機能の低下によるものです。
体質チェック
1.熱を生めるかチェック
□ 筋肉が少ない方だ / 体脂肪率が高め(25%以上)
□ 食事回数が3回/日以下、肉や魚などをメインとした食事は1日1回以下
□ 1日の歩数は、約8,000歩ない / 運動習慣がない
2.自律神経乱れてないかチェック
□ 夜型タイプ / 夜勤シフトなどの仕事をしている
□ 「眠り」に満足していない / 寝ても疲れがとれない
□ 1日の中で、オンとオフが切り替えられない
3. 保温できているかチェック
□ むくみやすい
□ トイレ(尿)の回数が日常的に少ない(日中で1〜2回)
□ 便秘体質
熱を生める体質になるための3つのルール
冷え症状の原因は見つかりましたか?先ほどもお伝えした通り「冷え」はあらゆる不調を連鎖させますが、反対に「熱を生める体質」を目指すことで、冷えの改善だけではなく、体調や体型面での不安や不満の解消につながっていきます。
まずは、取り入れられる習慣を見つけてきれい体質を目指しましょう!
ルール1. タンパク質リッチな食事にシフト

お肉お魚、卵などの動物性食材は、熱を体内で生み出してくれる「筋肉」の材料になり、さらに消化〜代謝の過程で熱を効率的に生みだしてくれます。(食事誘導性熱産生/ DITと呼びます)
食事制限は、ダイエットに効果的!?どころか、みるみるうちに筋肉低下と代謝ダウンに拍車をかけていきます。
※納豆やお豆腐などの植物性食材と比較して、女性が不足させやすいビタミン・ミネラルを効率的に補えます
まずは、昼食と夕食は片手手のひらサイズ(100-120g程度)を目安に、お肉やお魚などのメインディッシュがある食事で、タンパク質リッチな食事を目指しましょう。(朝食は卵が手軽でおすすめです!)
ルール2. 吐き出し&ストレッチ30秒習慣
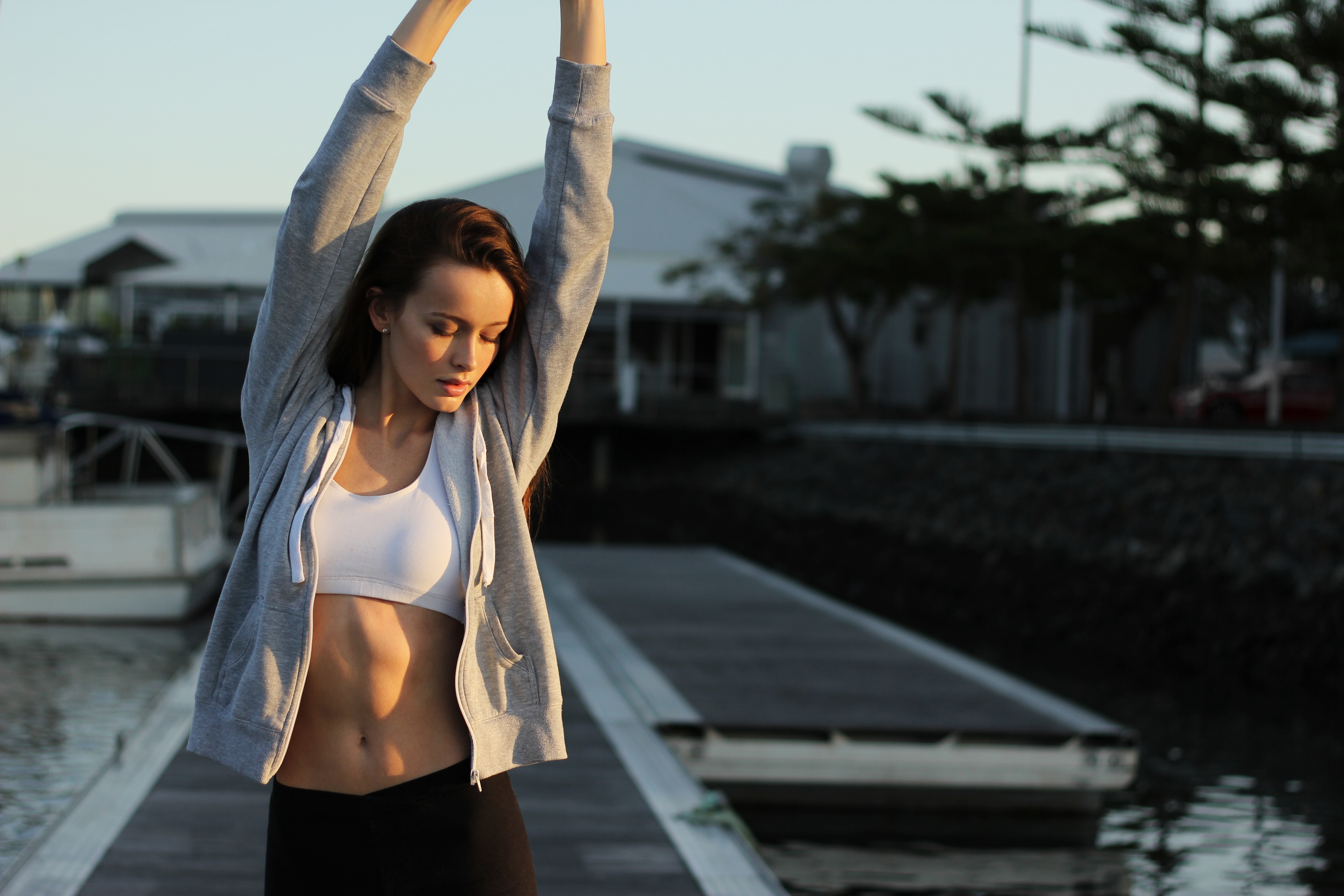
冷えの原因の1つ「熱を運べない=血流の低下」を解消していくためのアクションです。私たちは、緊張状態(=仕事中など、ONのシーン)が続くと呼吸は自然に浅くなります。この状態が慢性的になると、自律神経が乱れ食事も上手に消化〜代謝ができなくなります。
意識的に「吐く呼吸」を取り入れて、さらにアキレス腱や肩や首回しや大きく「う〜ん」と高く伸び!などをこまめに行い、筋肉や関節を動かし、血流を促進してあげましょう!
朝起きてトイレの後 / 日中トイレに立ったタイミング / 食事の前 / 休憩の時 / お風呂上がりなど、生活シーンを決めて取り入れることで習慣にしやすくなります。
※「吐く呼吸(呼気)」を意識して、たくさん吐き出すことで「吸う呼吸(吸気)」は自動的に深まります/どれだけ「吐けていないか」ということを実感できると思います
ルール3.入浴習慣でインナーケア習慣
忙しくて湯船に浸かる習慣がない…という方も、休日だけは「ゆっくり入浴タイム」を作ることがオススメです。
※シャワーしかない場合は、足湯がGOOD!
入浴によって、身体の内側の「深部体温」を上昇させ、眠りの質改善や疲労回復、血流UPなどが期待できます。
※身体の表面は「皮膚体温」
眠りの質は、一見冷えの改善には関係ないように思えるかもしれませんが、眠りを整えることで、代謝や食欲を担うホルモン分泌・自律神経からの体温調整に貢献するため、インナーケアにつながります。
まとめ
身体や心の仕組みやメカニズム、そして日々の食事と栄養、これらは全て繋がっています。
冷えを感じている方も、それ以外の不調を抱えている方も、少し視野を広げて、「熱を生める体質」を育んでみてください。
そのためにお伝えした3つのルール。
まずはスモールステップで「これならできる!」というもの、または自分自身の今までの習慣の中で「まずはこれ!」と感じたアクションを取り入れていきましょう。

