思い切って新しいことに挑戦したいと思いながら、日にちだけが過ぎていく。
やってみたいと思っていることがあるけれど、なんとなく先延ばしにしてしまう。
独立、起業したいと考えているが、今の仕事をなかなか辞められない。
考えても仕方ないと分かっているのに、考えてしまい、なかなか先に進めない。
周りの友人がどんどん変わっていくのを見て、自分だけが取り残されているように感じる。
そんなふうに、考えすぎて行動が止まってしまい、焦りや不安の気持ちだけが募っていくってことありませんか?
こんにちは。ヨガ&瞑想セラピストの 大野まさみ です。
私は統合医療的アプローチと体を使った心理療法のヨーガセラピーで、心と体の健康と、その人の持っている本来の魅力を引き出し、輝かせるサポートをしています。
今回は、なかなか行動できず止まってしまう方に、結果にコミットしないで動けるようになるコツをお伝えします。
分かっているのに行動できないワケ

私たちは、変わりたい、自分らしく生きたい、と思っていたり、口にしていても、実際には行動せずに、結局は何も変わらない。そして、いつまでも、何となく不足感を持ったまま生活する、という状態に陥りがちです。
当たり前のことですが、今と同じことをしていれば、現実は何も変わりませんよね。それどころか、確実に年だけはとっていきます。頭では分かっているのに、行動に移せないのはなぜでしょうか?
今の状態をキープしようとするホメオスタシス

例えば、北極でも南国に住んでいる人でも体温が常に36度程度をキープしますよね。また、暑くなったら汗をかいて体温を維持しようとする、ケガをすれば傷口をふさごうとする。これらはすべて「ホメオスタシス」の働きです。
身体が現状維持をしようとするだけでなく、心も今のままがいいと現状に留まる力が働いてしまいます。
前に進むために…

無意識に「変わらない」を選択し、新しい行動をストップさせていることをやめると、スムーズに動けるようになるかもしれません。
次に紹介する「3つのやめる」を試してみましょう。
1.考えるのをやめる
考えすぎて動けなくなるなら、考えるのをやめましょう。とはいえ、それができれば苦労はしませんよね。実は、考えすぎてしまう人は「やった後のこと」を考えているのです。まずは「やった後の結果を考えること」をやめてみましょう。
2.結果にコミットするのをやめる
「結果にコミットする」というCMがありますよね。
「ホメオスタシス」の働きにより、私たちの脳は「安定」を望み「変化」を避けようとします。ですので、結果にコミットすると、失敗したらどうしようなどと、先のことを考えて、動けなくなってしまいます。
新しい行動に対し、無意識に心がストップをかけてしまうのです。それに、挑戦しなければ、失敗のしようがありませんから、「コンフォートゾーン」にいることができます。新しい行動を起こすために、敢えて「結果にコミットする」をやめてみましょう。
3.悩むことを止める
考えてばかりで動けない時は、考えているのではなく悩んでいるのです。
自分が悩んでいる状態なのか、考えている状態なのかを区別して、まだ起こっていない未来を考える代わりに、行動に移せる具体的な方法を考えてみましょう。
以外と行動できる自分に気づくかもしれませんよ。
一歩前に進むためにできること

数字の力を使う
考えすぎて行動が止まりがちなら、数字の力を使いましょう。
例えば、3日間だけやる、1週間後に決める、〇月〇日から始めるなど、行動に数字を入れます。
昔ある方に、数字を入れるとは、命を吹き込むことだと言われたことがあります。命あるものは動きますよね。数字を入れることで、スタートが具体的になれば、もう動くしかありません。
ベイビーステップで進む

どんなことでも、最初の一歩がないと始まりません。ならば、最初の一歩のハードルを限りなく下げましょう。
このくらいなら出来そうなことを探すのです。
例えば、あなたが転職したいと考えていても、切羽詰まった理由がなければ、決断を先延ばしにしてしまうでしょう。辞めたいと言いながら、いつまでも同じ職場に居続ける、なんてことになりがちです。会社を辞める前に、転職先を探す、副業から始めてみるなど、ベイビーステップで進めばいいのです。その一歩が、どんな小さなことでも、転職のための行動を起こしている自分を、誇らしく思えるはずです。
心と体を緩めよう

心と体には関連があり、心身医学では「心身相関」といいます。
心が穏やかなら、体はリラックスしますし、イライラしていれば、体に力が入って固くなります。
自分の本来の力を発揮できるのは、リラックスしている時です。考えすぎて、心も体もガチガチになっていたら、心と体を緩めてみましょう。
心と体が緩むと、やる気が出て、意外と行動に移せたりするものです。
呼吸で気持ちをリセットする

気持ちをリセットする、簡単な呼吸法をご紹介します。
ヨガでは、「呼吸は心と体の架け橋」といいます。緊張したり、ストレスがあると、呼吸は浅くて早くなります。反対にリラックスしている時、呼吸は深くてゆっくりです。
ですから、リラックスしたければ、呼吸を意図的に「ゆっくり」にすればいいのです。
気持ちを切り替える1:2の呼吸
吸う息が1に対し、2倍の長さで息を吐きます。
できれば、目を閉じて1~2分間行ってみましょう。
4秒で吸ったら、8秒かけて吐きます。
10秒で吸ったら、20秒で吐きます。
吐く息が長ければ、正確に倍の長さでなくても構いません。
吐く息と一緒に、考え事も吐き出してしまいましょう。
「結果」でなく「今」にコミットする

小さな一歩を踏み出すことができたら、現実は必ず動き出します。
もし考えすぎていたら、目を閉じ、ゆっくり息を吐いて、体と心を緩ませましょう。「結果」にコミットする代わりに「今」にコミットしましょう。
どうせ考えるなら、やりながら考えるくらいの軽い気持ちで、小さな一歩から始めてみませんか? きっと気づいたら、以前の自分が懐かしく思えるくらいに、見える景色が変わっているはずですよ。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて、外出自粛に伴う自粛疲れ、収入の減少と経済不安、精神的不安・・・
いつまで続くかわからないこの状況の中、全ての人がそれぞれに問題を抱え、新たな生活様式を受け入れながら毎日を過ごされていらっしゃることと思います。
今はまず、新型コロナウイルスに 自分が感染しないようにすること、自分から、家族や友人、パートナー等、 大切な人にうつさないことといった感染対策の実践とあわせて、未来のための準備も大切です。
新型コロナウイルスウイルス終息後の世界において、今よりも1年後、2年後の新たな世界、新たな生活様式の中で、本来の力をしっかりと発揮できるよう、自分自身の体力や免疫力を維持しておくことや、人と人との繋がりや絆を、強めておくことなどもとても重要です。
ヨガ、マインドフルネス瞑想の講師をしています、小田祥子です。
今日は、こんな時だからこそ、ポジティブなマインドを育てる「マインドフルネス瞑想法」についてご紹介します。
健康と幸福に必要な脳内ホルモン
「健康」でいたり、「幸福感」を感じさせるには、2つの脳内ホルモンが関係しています。
愛情ホルモン「オキシトシン」
昼間自宅でテレビの情報番組をみていたら、「脳内ホルモン」の話が出てきました。
ショッピングモールのような場所で一般の方に声をかけ、簡易で作られた試着室のようなスペースの中で(恐らく数分?)二人で抱きしめ合ってもらう。

その前後で、唾液中のオキシトシンというホルモン量を測定し比較するという実験です。
ご夫婦や恋人同士、中には女性の友人同士という二人組もいましたが・・・。
結果は、被験者の全員に、唾液中に含まれるオキシトシン量が増加する(特に女性は男性に比べより顕著に)反応がみられた、というものです。
オキシトシンが「愛情ホルモン」という異名を持つことが改めて良くわかる実験結果ですね。
人と触れ合うこと=「グルーミング」や、触れられることによる「タッチング」の癒し効果についても紹介されていました。
幸せホルモン「セロトニン」
オキシトシンとは違う脳内ホルモンに、「セロトニン」があります。よく幸せホルモンと言われるものです。
セロトニンは、集中力を高め、明るく前向きな心を作り、うつ病の治療や予防にも深く関わることから注目されている脳内ホルモンです。
セロトニンは腸内で産生されるのですが、それ以外に、日光を浴びること、一定のリズム運動等によって脳内での分泌が促されます。
オキシトシンとセロトニンは両方とも、脳心を安定させ、体の免疫力を高めます。つまり、健康と幸福には必要不可欠なホルモンなのです。
家族やパートナーとの触れ合い、朝起きて朝日を浴びたり、運動したり、そういった事で健康で幸福感をアップできます。
状況の変化に合わせて、健康でいる工夫が必要
外出自粛によって、ストレスを感じ体にも悪影響が出てきているようです。
私が勤務しているクリニックでは、糖尿病で通院加療されている患者様の血糖値やHbA1cという数値が、ここ1ケ月ちょっとで全体的に上昇傾向にあり、コロナウイルス感染拡大の影響によるところかなと、先生が話していました。
運動不足の上に、”ついつい食べてしまう”過食傾向。不安や、人と会う機会が減ることでの寂しさといった心因的要因でも、ストレスホルモンが増加し血糖値を上昇させます。
血糖コントロールが悪い状態が長期間続けば、糖尿病性網膜症という目の病気、糖尿病性腎症(腎臓の病気)や、免疫力低下などの合併症リスクが高くなります。
変化を楽しむ
人間は現状維持をしたがる生き物です。強制的に変化を求められる今、ストレスを感じるかもしれません。しかし、その変化を楽しんだり、今まで当たり前だと思っていたことに感謝したり、変化を楽しんでみましょう。
人と人とのコミュニケーションにおいて、物理的な距離が近くても、「心が離れているなー」と感じることがあるように、愛情や幸福感、感謝の気持ちを感じるときの心の距離というのは、必ずしも、物理的な距離に比例するものではありません。
最近巷で流行ってきたZoomを活用したオンラインの飲み会やランチ会は、場所は違っても同じ時間を共有し、お互いの表情を観ながら言葉を交わすことができる、ただそれだけのことですが、実は脳にとても良いのです。

私のヨガスタジオでも、オンラインのヨガと瞑想のクラスを先月よりスタートしました。
スタジオでのレッスンと同じようにはいかないところもありますが、画面上のお客様の表情や、体を動かしている際のご様子を観ながらクラスを進める中で、
“離れていても、私とあなたは 共に在る“
“離れていても、皆共に在り、繋がりの中に生きている“
「yoga」という言葉が元々持っている「繋がる」という意味を思い起こさせ、そういった体験が、とても有意義だということを改めて実感しました。
意識を向ける先を変える

変化を楽しんだり、変化に対応するためには、今までとは意識を向ける先を変える必要があります。
オンラインでの交流も、心身の健康を保つのにとても良い実践になりますが、自宅にいる時間を充実させるために、家族との時間と自分の時間について、今改めて見つめなおす時期にあるのではと思います。
意識を「今」という瞬間に集中させる、即ち「マインドフルネス」と「瞑想」のトレーニングは、自身の内側を深く見つめたり、新たな気づきやひらめきを得るのにとても良い練習になります。
不安な心を、穏やかで前向きな状態に整える「マインドフルネス瞑想」と、日常で簡単に行える「プチ瞑想法」についてご紹介します。
マインドフルネスについて
「マインドフルネス」は、元々仏教の言葉です。
ベトナムの禅僧ティク・ナット・ハン師が、禅の教えである「念(パーリー語で“サティ”)」のことを、英語で「マインドフルネス」と表現したのが始まりです。
Google社の企業研修にこのマインドフルネス瞑想が取り入れられたことをきっかけに、欧米の先進企業をはじめ、教育学、心理学、医療など様々な領域など、様々な分野で知られるようになりました。
ポジティブなマインドを育てる「マインドフルネス瞑想法」
まず自分自身の呼吸に意識することに集中することから始めていきます。
買い物の予定や、誰かに言われたこと、思考には未来や過去へと彷徨いやすい特性があるが故に、今この瞬間にある自分の呼吸や、体を丁寧に感じるように努めます。
呼吸があって、今の命があることや体がここにあって、リラックスしていること、心臓が鼓動していることなどを坐って目を閉じ、ただただ感じるという作業が、「私はここに確かに存在し、心臓が鼓動している」という気付きになり、自己受容や自信、感謝といったポジティブな感情を育むことに繋がります。
坐って目を閉じる「静座瞑想」は、初心者の方が一人でやるにはちょっと難しく、理想的な瞑想状態を獲得するのにはガイドがあった方が良かったり、何度か練習が必要です。
もう少し簡単な方法のマインドフルネス瞑想で「食べる瞑想」というものがあります。
手軽な瞑想「食べる瞑想」

“食べる”ことに集中して、良く味わって食べるという瞑想法です。
テレビを見たり、誰かとのお喋りもやめて、食べることだけに集中します。
口に入れた時の温度や舌触り、咀嚼する時の硬さや柔らかさ、味も 甘み、塩味、酸味、苦み、辛味・・・味覚に集中して繊細に丁寧に味わいます。
食べ物と、この恵みを頂いている地球の全ての存在に感謝する気持ちを持つことも重要な要素ですが、何より味覚を研ぎ澄ますことそのものが、感情を穏やかにし集中力を高めます。
「味わう」という意識と集中力が必要ですが、美味しいものを本当に味わって美味しく食べることそのものが幸福なのですから、美味しさも増し増しになって良いと思います。
美味しいお肉でも、スイーツでも、食べるものは何でもよいですが、自分が心から美味しい、味わいたいと思える自分なりのご馳走を用意して、ぜひ試してみてください。
家族と一緒に「食べる瞑想」

食べる瞑想ができたら、今度は家族の誰かと一緒に、この食べる瞑想を実践してみます。
テレビはつけずに、よぉく味わって食べることだけに集中する時間を10分ほどとったら、その後は言葉を交わしながら、一緒にいるご家族・・・パートナーやお子さんの表情をよくよく観察してみましょう。
会話をする中で自分の心が何を感じているのか、丁寧に眺めるようなつもりで自身の心の様子も感じてみます。
瞑想で健康と幸福感をアップ

瞑想の基本は、意識を何か一つに集中するということです。
ベーシックな瞑想ではよく、呼吸に意識を集中するところからスタートしますが、日常に置き換えるなら、誰かと共に過ごしているときであれば、相手の表情を丁寧に観察し、その言葉に耳を傾け、その瞬間ごとの自身の感情の移ろいすらも、ただあるがままに感じ、体験するということになります。
それは、一瞬一瞬を大事に過ごすということであり、人生の、今日という一日の、一瞬一瞬を丁寧に生きるという実践です。
何気ない日常であっても、意識の在り方によって日々の気づきや充実感には大きな差が生まれ、丁寧に生きようとする意識によって、幸福だと感じる度合いもより高まるはずです。
脳科学者の中野信子さんの著書「脳科学からみた『祈り』」 の中で、感情とオキシトシンの関係について以下のように解説されています。
「大切な誰かを思うとき、心がその人への愛情にあふれるとき、脳内にはオキシトシンが大量に分泌されています。大事な人が幸せになってほしい。自分のためだけでなく、誰かのために祈る。
その祈りがそのまま、自分の脳にも良い影響を及ぼすものとなっていくのです。」
(第1章 脳に与える祈りの影響 より)

家族と共に過ごす時間の中で“幸福だ“と感じる瞬間には、愛されたい、愛したいといった感情が伴い、一人一人が自身の内側にある愛情や慈しみの感情に目覚めることによって、脳内のオキシトシンが増加し、免疫力や記憶力、思考力までも高めます。
外出の自粛をはじめ、これまでの生活様式を改めなければならず、思うようにならない状況の中皆苦しい思いをしているかもしれませんが、今こそ私たちには、一日一日を丁寧に生きることが求められています。
これまでの価値観や、これまでの自身の生き方を見つめなおす機会となっている今の状況の中で、大切な人と支え合いながら、今ある幸福と豊かさに気づき、目の前にある危機を乗り越え、より良い未来へと前進するための心身のエネルギーを高めておきましょう。
〇美味しく丁寧に味わう「食べる瞑想」
〇座って目を閉じたまま1分間、呼吸とからだを丁寧に感じる静座瞑想
良かったらぜひ試してみてくださいね。
「私たちの多くは、イメージの世界から抜け出ることができません。
苦しみという心の形成物をあるがままに認め、
抱きしめる実践をしましょう。
それができれば、前に進めます。
人生は不可思議で素晴らしいものに満ちていることが見え、
今ここで幸せに生き、人生を一変させることができます。」
“マインドフルネス”の生みの親 ティク・ナット・ハン師の言葉
(「和解―インナーチャイルドを癒す―」 より)
こんにちは。マインドフルネストレーナーの小田祥子です。
私は普段看護師をしながら、年間3000名以上の方にヨガや瞑想などで、心と体の整え方を指導しています。
現在、新型コロナウイルス感染拡大で、医療機関も世間も混乱状態です。このような先の見えない不安を感じると、人間は自分勝手な行動をしてしまいます。
こんな時だからこそ、皆さんに不安な心との向き合い方をお伝えし、「今日を大事に生きて欲しい」と願い、このコラムをお届けします。
私自身の子供の頃の出来事を交えて、思い込みと不安に溢れた人生と、そこからの解放について、説明していきます。
子供の頃の出来事

「祥子ちゃんのパンツはボロボロすぎて、おばあちゃん 恥ずかしくて干せないよ。お金、1000円あげるから、明日学校帰りに買ってきなさい。」
私が中学3年生の時の、祖母の言葉を、洗濯物を干しながら、今日ふと思い出しました。
昨今のコロナウイルス拡大防止のための外出自粛要請の影響もあって、家にいる時間が長いせいか、家事の合間に、ふと子供の頃のことを思い出したりします。
私が中学3年の夏休みのことです。
母が飲酒運転で近所の畑に車ごと突っ込み、その翌日、母は叔父や祖父に引きずられるようにして、アルコール依存症専門病院に(強制的に)入院しました。
私はその日から、祖父母宅での生活が始まり、1週間ほどたった時の祖母の言葉でした。
中学3年の私は恥ずかしさのあまり、その言葉でしばらく泣いていましたが、今思い出すと笑い話で、私を気遣って言ったであろう祖母の言葉を思い出しました。
母の「キッチンドリンカー」生活は、私が小学生に上がった頃から徐々にその兆候が始まっていました。
テーブルの上の焼酎の紙パック、たばこの吸い殻で山盛りになった灰皿、台所の流しに残った母が吐いたもの、学校から帰ると閉め切った部屋に、色んな臭いが立ち込めているのが当時の私の「日常」になっていました。

酔っぱらった母の説教が始まると、大抵、最後は暴力が始まり、窓から裸足で逃げていました。
「こんなのがいつまで続くんだろう」
「望まれなかったのなら生まれてこなければ良かった」と、よくそう思ったものです。
一度も私を探しにこない父親のことも、愛情などなく捨てられたようなもの。そんな風に思っていました。
母の死と父との再会
私が40歳になった一昨年、母が孤独死し、遺体は腐敗した状態で発見されました。
7年連絡を取らずにいた私は、後悔と自責の念もありましたが、両親たちが戸籍上夫婦のままだったので、兎にも角にも37年会っていなかった父を早く探さなければなりませんでした。
子供の頃、特に望むことのなかった父との再会と結末は、それまで幾度となく想像した、どの未来予想とも違っていました。
父は、私の顔を見て泣いていました。しかし、脳出血の後遺症の影響で父の思いや昔の事などを、父の口から聴くことはできず、父を怒ることもできませんでした。
「母を亡くし孤独になった」はずの私は、育った故郷には帰る場所はなくなりましたが、父方の親族が皆笑顔で私を迎えてくれて、予期せず20人を超える親戚ができました。
当時の事、これまでの事、私の経験した過去記憶のフラッシュバックについて、ヨガのこと、マインドフルネスのこと、
今、本にする準備を進めているところなのですが(詳細が決まり次第、、ご紹介できればと思います)・・・
新型コロナウイルスの不安への対処法
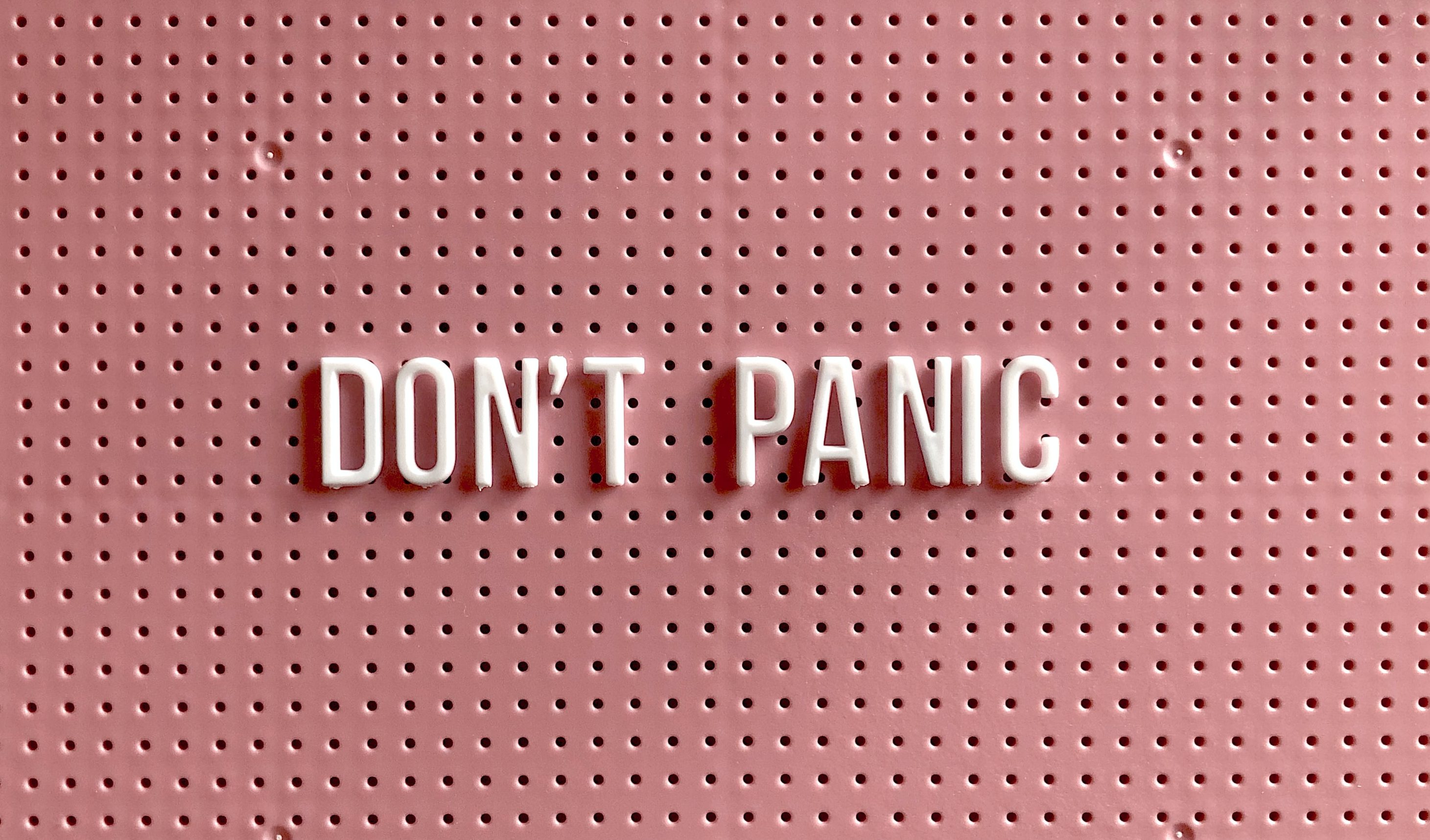
新型コロナウイルスの感染経路は接触感染又は飛沫感染です。
対策は一番は手洗い、洗っていない手で顔、口、目などを触ると感染が起きます。
マスクは飛沫を飛ばさないこと、花粉でのどや鼻の粘膜が荒れるのを防ぐ効果があります。
ウイルスの大きさより網目の大きい市販のマスクは、ウイルスそのものを体に入れない効果はありませんが、感染していても無症状であるケースが多いということを考えれば、飛沫を飛ばさない、人にうつさないために、マスクをつけることは誰かを救う行動と言えますね。
電車内にいてくしゃみが出そう、でもマスクがない場合、袖の肘の辺りで口鼻を覆う。それもその時にできる適切な実践です。

手で口や鼻を覆うと、その手で手すりやドアノブ、エレベーターのボタン、食事をするときのテーブルに触れて感染を広げかねないことを知っておきましょう。
もし発症したら?
自分を信じて治療に専念するしかありません。
不安な時の心の在り方

辛い状況にあるときの多くが、私だけではなく、他の誰かも同じように辛さや苦しみのなかにあるもの。
不安や恐れで取り乱す必要はないけれど、無関心であってはいけない。
正しい情報を基に、自分にできる限りの対策をする。
正しい知識、それに基づく実践、前向きな姿勢が、世界を救う力の一部になる。

”委ねる”とは人生における難しい実践ですが、繋がりの中に生かされていることを知り、
一瞬一瞬を味わうように、
マインドフルに、
今日という日を大事に生きていきましょう。
こんにちは。
マインドフルネストレーナーの小田祥子です。
私には、目の前の人の言葉遣いや柔らかかったり、声が個性的で尚且つ素敵だったり、人の「言葉」や「声」が、美しい音色のように感じられることがあります。
水と言葉の実験
皆さんは、江本勝著「自らの伝言」という写真集をご存知ですか?

よくあるきれいな六角型の結晶から、葉っぱの葉脈のような結晶、丸い形に近かったり、ぐちゃぐちゃな形のものまで、ページをめくるごとに様々な形の水の結晶の写真がでてきます。
「自らの伝言2」で著者はお水に音楽を聴かせて、それぞれ一定の条件のもとに水を凍らせ、氷結結晶を撮影したものを写真集としてまとめられました。
http://www.spoonnet.jp/interview/176.html
水は波動を受け取る性質をもっているということを実証しました。
- 「モルダウ」や「四季」などのクラシック音楽を聴かせた水は、美しく素晴らしい結晶を見せました。
- ところが、ヘビーメタル音楽を聴かせた水では、形がバラバラな粒が並び、結晶が壊れてしまう様子が見て取れました。
最終的には、言葉を書いた紙をラベルに貼り付けて同様の実験を行います。
- 「ありがとう」と「ばかやろう」の紙を容器に貼ると、「ありがとう」では六角型の綺麗な結晶
- 「ばかやろう」のほうは、ヘビメタ音楽と同様結晶がぐちゃぐちゃに壊れてしまいました。
私たちは言葉で変わる

私たちのからだの60%以上はお水で形成されています。
心のこもった「ありがとう」という感謝の言葉、
愛や思いやり、慈しみの気持ちを伝える言葉、
ポジティブで健全な言葉、
「ありがとう」「よく頑張ったね」という感謝やねぎらいの言葉を、自分自身のからだとこころに、かけてあげるのも良いと思います。
(私のヨガのクラスでも、終わりのご挨拶のときなどにこのワークを入れたりしています)
否定的、または暴力的で不健全な言葉や、ネガティブな言葉は、その逆の、好ましくない影響として相手の人や自分自身へと返ってくるものなので、できるだけ慎む必要があるということです。
辛い状況の渦中にあるときは、ネガティブな思いや言葉がつい出てくるかもしれませんが
そんなときは・・・
蓋をしようとすることも余計なエネルギーを浪費し、却ってこころが疲弊してしまいかねないので
「辛かったね」
「悔しかったね」
「大丈夫だよ」
「よく頑張ったね」
と、優しく労う言葉を自分のからだとこころへかけてあげましょう。
愛と優しさで労わり、疲れが少し癒えてくると、そこから力が沸いてくるはずです。
私たちのからだの60%以上はお水で出来ている。
愛ある言葉を実践し、きれいになりましょう。
こんにちは。
マインドフルネストレーナーの小田祥子です。
私は普段、看護師をしながら、ヨガや瞑想の指導をしています。
皆さんは、ストレスで過食に走ってしまう事はありませんか?
私も、以前、夜勤専任の看護師として老人ホームに派遣勤務していた頃、夜勤明けで帰宅すると、異様に食べている自分がいました(笑)
“食べている”というより、“食べ続けてしまう”という感じかもしれません。
激務で過食が止められなかった過去

甘いものもしょっぱいものも食べたくて、あれもこれも食べるのですが、お腹がいっぱいになったのか、まだ空いているのかもわからなくて、食べ続けてしまいます。
夜勤明け、特に忙しくて休憩がとれなかった夜勤を終えた後はそうなりました。
派遣先で多少時間は異なりましたが勤務時間は、前日の16:00位から翌朝9:00(または10:00)まで。
夜勤中急変やお看取りがあると、記録物や書類整理が終わらず、長くても1時間程度ですが残業になりました。
夜勤中はゆっくり食べる間もなく動き回っていたので、勤務が終わりほっとすると飢餓状態のような空腹感がやってきます。帰宅途中のスーパーではやたら食べ物を買い込みすぎたりしていました。
夜勤が明けた翌日にヨガのレッスンの仕事がると、胃も体も気分も重くて「良くないなぁ」と反省していました。あの当時は、だいぶ無理をしていたなぁと今更ながらにふと思い出しました。
皆さんも、自分にとても無理をさせて頑張り過ぎている時に「過食」してしまう経験はありませんか?
ストレスと過食の関係

ストレスの高い状態の時には自律神経は交感神経優位となり、気分は興奮気味、呼吸も早めで覚醒状態。血流は骨格筋に集中し、胃腸の働きが弱まっている状態です。
ストレスによる「過食」のメカニズムは、この興奮状態を食べることによって副交感神経優位にしようとしている無意識の反応と言うことができます。
有酸素運動も副交感神経優位の状態へと働きかけ、ストレスによる反応を和らげる効果が期待できるので、呼吸法やヨガも「過食」という代償反応を防いでくれます。
ここでお勧めしたいのが、「食べる瞑想」です。
食べる瞑想
マインドフルネスの瞑想には、「食べる瞑想」というものがあり、マインドフルネスのワークショップやトレーニングでは必ず実践する瞑想の一つです。
【食べる瞑想やり方】
食べ物を「味わって食べる」ただそれだけになります。

丁寧に味わって食べるので、食べているときその食べ物に集中し、味や食感をよく噛みんで食べて味わいます。
その日の予定や誰かに言われたことなどに注意をそらさないようにして、会話も食べる瞑想中は慎みます。
しょっぱい、甘い、酸味や苦味、食感、舌触り、丁寧に感じながら
目の前の食べ物や、こうして自分が食べていることへ感謝を感じます。
食べている場所が素敵な場所なら、その空間や景色も味わいます。空やあたたかい陽射し、心地よい風を感じるのも良いです。
“丁寧に感じる”という作業は、怒りや恐怖に関係する扁桃体を鎮静させ、心を穏やかにしますし、感謝の気持ちを持つことは愛情ホルモンの「オキシトシン」の分泌を促します。
本当に美味しいものを、丁寧に味わって食べることは、優しさや穏やかさを取り戻し、食べている時の所作も自ずと美しくなるはずです。
意識すること、努力と継続は必要になりますが、ダイエットにも有効だと思います。
食べ過ぎてしまうと効果はなくなってしまうので適量を意識して(笑)
時には大切な誰かと一緒に、それも良いでしょう。
こころから「美味しい」と感じる食事を感謝の気持ちとともに味わって食べる、「食べる瞑想」でキレイになりましょう。

