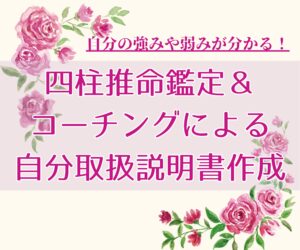玄米が健康に逆効果とされる原因と対策について!おすすめ玄米も紹介
玄米はその豊かな栄養価から「スーパーフード」としても注目され、食生活に取り入れる方が増えています。
一方で「玄米は危険」「体に悪い」といった情報に触れ、不安を感じている方もいるでしょう。実際に体にいいと思って始めた玄米が、食べ方次第で逆効果になることがあるとご存知でしたか?間違った摂取方法によりお腹が張ったり、胃腸の調子が悪くなったり…そんな声も少なくありません。
この記事では、玄米が体に逆効果と言われている理由や、玄米の正しい食べ方、選び方を、メリットやデメリットと共に解説します。正しい知識を身に着けることで、玄米は健康に役立つ強い味方になります。
初心者にもおすすめの玄米も紹介しますので、安全に美味しく楽しみましょう。
玄米とはどんなお米?白米・発芽玄米との違いや玄米毒と言われる理由を紹介
玄米は、精米されていない稲の実からもみ殻だけを取り除いたお米のことです。私たちが普段食べている白米になる前の状態を指します。
ちなみに、白米は玄米から糠(ぬか)や胚芽の部分をさらに取り除いたものです。
玄米の栄養成分と白米との違い
玄米は、表皮(ぬか)や胚芽がそのまま残っているため、白米に比べて栄養価が非常に高いのが特徴です。主な玄米の栄養成分は以下の通りになります。
- 食物繊維:白米の約6倍。腸内環境を整える効果が期待でき、便秘の改善に役立ちます。
- ビタミンB群:代謝を助け、疲労回復やストレス軽減に効果的です。
- マグネシウム・鉄分:血圧の調整や貧血予防に役立ちます。
また、玄米は血糖値の急激な上昇を抑える「低GI食品」であり、白米よりも血糖値の上がり方が緩やかです。
これらの栄養素がバランスよく含まれていることで、血糖値の急上昇を抑え、糖尿病予防や生活習慣病のリスク軽減にも期待できます。
発芽玄米との違いと特徴
発芽玄米は、玄米を水に浸してわずかに発芽させたお米です。発芽の過程で玄米の酵素が活性化しGABA(ギャバ)が増加します。
GABAはストレス軽減や血圧の安定化、睡眠の質向上などの効果が期待されており、健康面でのメリットが注目されている成分です。
また、発芽玄米はぬか層が柔らかくなるため、通常の玄米よりも消化しやすく、食感も白米に近いので食べやすいと言われています。炊飯時の長時間の浸水が不要で、手軽に調理できる点も魅力です。
「玄米毒」と言われる理由と噂の真偽
「玄米は危険」「玄米は毒」といった情報を目にすることがありますが、これらの主張には科学的根拠が乏しいとされています。こうした噂の背景には、玄米に含まれる「アブシシン酸」や「フィチン酸」といった成分が関係しています。
特に「玄米毒」という言葉で問題視されるのは、玄米に含まれるフィチン酸という抗栄養素です。フィチン酸は体内で鉄や亜鉛、カルシウムなどのミネラルの吸収を妨げる性質があり、この点から「毒」と誤解されることがあります。
しかし、フィチン酸には強い抗酸化作用もあり、がん予防や老化防止に役立つ研究結果も報告されています。また、通常の食生活で玄米を適量食べる場合、ミネラル吸収への影響はほとんど問題にならず「玄米=毒」とする見方は過剰な誤解といえるでしょう。
(参考:厚生労働省PDF「既存添加物の安全性の見直しに関する調査研究」)
玄米に含まれる成分は過剰に摂取しない限り健康への害は少なく、むしろ健康維持にプラスに働くことも科学的に示されています。
玄米を毎日食べ続けることで期待できる効果&メリットについて

玄米は「完全栄養食」とも言われるほど栄養価に優れた食材です。継続して食べることで健康面だけでなく、美容や体型維持にもメリットがあります。
ここでは下記の2点について詳しく解説します。
- 満腹感とダイエットへの相乗効果
- 美肌と美髪をサポートする栄養素
満腹感とダイエットへの相乗効果
玄米は白米に比べて噛み応えがあり、自然と咀嚼回数が増えます。そのため、満腹感を得やすくダイエット効果が期待できます。
さらに、食物繊維が豊富で消化に時間がかかるため腹持ちがよく、間食や食べ過ぎの予防にも効果的です。GI値が低いため血糖値の急上昇を抑え、体脂肪の蓄積を防ぐ効果も期待でき、無理のないダイエットをサポートしてくれます。
美肌と美髪をサポートする栄養素
玄米には、美肌やアンチエイジングに役立つビタミンB群(B1・B2など)やビタミンE、亜鉛・鉄分などのミネラルが豊富に含まれています。
ビタミンB群は肌の新陳代謝を促し、肌荒れやニキビの改善に効果が期待できます。また、ビタミンEやフィチン酸などの抗酸化成分は老化を防ぐ働きがあるので、髪や肌のツヤを保ち、体の内側から美しさをサポートしたい方にぴったりの食材です。
玄米は体に悪いって本当?健康に逆効果とされる理由や主な症状を紹介

玄米は健康に良いとされる一方で「体に悪い」「逆効果になる」といった声も聞かれます。実際に、玄米を食べ始めてから体調を崩したという人もおり、その理由にはいくつかの要因が関係しているようです。
ここでは、玄米が逆効果とされる主な理由や、起こり得る体調不良の例を紹介します。
胃腸トラブル(腹痛・下痢)のリスク
玄米は白米に比べて食物繊維が非常に豊富です。特に硬いセルロースという不溶性食物繊維に覆われているため、消化に時間がかかります。不溶性食物繊維とは水に溶けないタイプの食物繊維のことで、玄米以外にも野菜や豆類、キノコ類などにも含まれています。
そのため、胃腸が弱い方や玄米に慣れていない方が、よく噛まずに食べたり、炊き加減が硬い状態で食べたりすると下記のような症状を引き起こす場合があるのです。
- 腹痛
- 下痢
- 便秘
- 胃もたれ
また、不溶性食物繊維を過剰に摂取すると、お腹の張りや痛みを感じやすくなるため、食べ方には注意が必要です。
農薬・重金属が残りやすい?安全面の注意点
玄米は精米されていないため、表皮に農薬や重金属などが残りやすいとされています。特に農薬は、脂質の多い糠や胚芽部分に蓄積しやすく、水田由来の「無機ヒ素」も玄米の外皮に多く含まれます。
無機ヒ素は国際機関で発がん性が高いとされ、日本でも基準は設けられていますが、毎日食べる場合は摂取量に注意が必要です。乳幼児や多量摂取者は特に気をつけるべきだと海外で勧告されているため、玄米を選ぶ際は無農薬・有機栽培のものや、安全性が確認された商品を選ぶことが推奨されます。
肝臓・腎臓に負担がかかる可能性
玄米に含まれるフィチン酸やたんぱく質の消化抑制成分は、摂りすぎると体に負担をかける可能性があるとされています。特に、消化器官が弱っている方や持病がある方は注意が必要です。
また、玄米はカリウムやリンを多く含むため、腎臓病の方にとっては摂取量に配慮すべき食品といえます。ちなみに、健康な人にとって玄米が肝臓や腎臓へ明確な悪影響を与えるという科学的根拠は乏しいものの、体調や疾患の有無に応じて、医師の指導のもと取り入れると安心です。
玄米を食べると癌になるのはウソ?その真偽と根拠について
「玄米を食べると癌になる」といった噂を耳にしたことがあるかもしれませんが、現時点で玄米の摂取が直接的に発がんリスクを高めるという科学的根拠は存在しません。
この噂の元となっているのは、玄米に含まれるフィチン酸という成分です。フィチン酸はミネラルの吸収を妨げる「抗栄養素」とされる一方で、抗酸化作用があり、がんの予防に役立つ可能性も報告されています。
また、「無機ヒ素」が玄米の外皮に含まれるという事実も噂拡大の一因ですが、日本国内では安全基準が設けられており、通常の摂取量で健康被害が出るリスクは極めて低いとされています。
つまり、正しい方法で選び、適量を守って食べていれば、玄米が発がんの原因になる心配はないといえるでしょう。
玄米を食べてはいけない人の特徴とは?
玄米は栄養豊富ですが、すべての人に合うわけではありません。特に体質や健康状態によっては、玄米の成分が負担になることがあります。以下のような方は注意が必要です。
| 過敏性腸症候群(IBS)や胃腸が弱い人 | 不溶性食物繊維が多く、腹痛や下痢、ガスが起こりやすくなります。 |
| 幼児や高齢者、咀嚼力が弱い人 | 玄米は硬く消化に時間がかかるため、消化不良の恐れがあります。 |
| 貧血やミネラル不足の人 | フィチン酸がミネラル吸収を妨げる可能性がありますが、玄米自体はミネラルも豊富です。 |
| 腎臓病の人 | カリウムやリンの摂取量に注意が必要です。 |
| 冷え性や低体温の人 | 東洋医学の一部では玄米を「身体を冷やす食品」とし、体質によっては合わないとされます。 |
| 体調不良時 | 胃腸が弱っている時は負担になるため、柔らかく調理するなどの工夫が必要です。 |
玄米を食べる際は、体調や体質を考慮し、無理せず少量から試しましょう。
玄米による逆効果を避けるには?適量・効果的な食べ方・食材の組み合わせを紹介
玄米は栄養豊富な食材ですが、食べすぎや誤った調理により、胃腸への負担や栄養吸収の妨げとなることがあります。逆効果を防ぐために、以下のポイントを押さえて取り入れましょう。
玄米の1日あたりの適量はどれくらい?
玄米の1食あたりの適量は、個人の活動量や消費エネルギーによって異なります。目安として男性180g〜200g、女性140g〜180g(お茶碗一杯軽く盛りつけて約150g程度)とされているため注意しましょう。
ダイエット中であっても、脳の唯一のエネルギー源である糖質を確保するため、適量をしっかり摂ることが推奨されます。
玄米の効果的な食べ方とおすすめの組み合わせ
玄米は食物繊維が豊富で腸内環境を整えるのに効果的な食材ですが、さらに効果を高めるためには、食べ方や組み合わせにも工夫が必要です。
まず、玄米はよく噛んで食べましょう。噛むことで唾液と混ざり、消化を助ける酵素の働きが促進されます。また、炊く前にしっかり浸水させると、玄米の硬さが和らぎ消化しやすくなります。
玄米と相性が良いのは、発酵食品やビタミンCを含む食材です。特に納豆やキムチ、味噌汁などの発酵食品は腸内の善玉菌を増やし、腸活をサポートしてくれます。これらの食材と一緒に摂ると、腸内環境が整い、栄養の吸収もスムーズになります。
また、ビタミンCを含む野菜や果物を合わせると、玄米に含まれる鉄分の吸収率が上がり、貧血予防にも役立ちます。
このように、玄米を効果的に食べるためには、よく噛むことと腸に良い食材との組み合わせを意識することがポイントです。
玄米をおいしく安全に食べたい人必見!初心者にもおすすめの玄米
玄米を取り入れようと考えている場合、選び方も重要です。正しく選べば、初心者でもおいしく安全に楽しむことができます。特に以下のようなタイプは、初めての方にも扱いやすいでしょう。
- 無農薬・有機栽培の玄米
農薬や有害物質が残りやすい糠部分を含むため、農薬の使用を抑えた「有機JAS認証」や「特別栽培米」など、安全性の高いものを選ぶと安心です。 - 発芽処理済み・発芽しやすい玄米
「ロウカット玄米」「ネオ玄米」「無洗米玄米」などは表面加工がされていて浸水が短時間で済み、白米と同じように炊けます。調理がラクで、消化にもやさしいのが魅力です。 - 低温乾燥の玄米
通常の玄米よりふっくら炊き上がるため、硬さやパサつきが苦手な方にもおすすめ。食べやすく、玄米初心者や咀嚼力の弱い方にもぴったりです。
このように、栽培方法・加工方法・調理のしやすさを意識して選べば、健康的でおいしい玄米生活を無理なく続けることができます。
金芽ロウカット玄米(東洋ライス)

参考価格:2kg2,700円(税込)
金芽ロウカット玄米は、特許技術により玄米の表面にある硬いロウ層を均等に取り除いて加工されています。玄米の栄養価はそのままに、白米のようなふっくらとした柔らかい食感を実現。吸水性が向上しているため、通常1時間程度の浸漬で炊飯可能であり、無洗米なので手軽に調理ができます。
やわらかい玄米(ヤマトライス)

参考価格:900g1,590円(税込)
やわらかい玄米は、独自の特許技術で加工されているため白米と同じように炊飯できます。軽く洗った後、炊飯器の白米モードで炊くことができ、基本的に浸漬は不要です。通常の玄米よりも消化しやすいとされており、胃腸が弱い方や初めて玄米を食べる方にも適しています。
スマート米/無洗米玄米(SMARTAGRI FOOD)

参考価格:1.8kg2,980円(税込)
スマート米は、ロウ層に傷をつける加工が施されているため吸水が早く、浸水が不要で炊飯器の「白米モード」で炊くことができます。加工されていない一般的な玄米と比べても、栄養価がほとんど損なわれません。また、白米と混ぜて炊く場合も浸水や水加減の調整が不要で簡単です。
簡単おいしい玄米(神明)

参考価格:1.8Kg1,818円(税込)
簡単おいしい玄米は「スチームクリーン製法」という独自技術を用いて加工されています。高温スチームで表面をなめらかにすることで、通常よりも短い約1時間の浸漬でおいしく炊き上がるのが特徴です。GABAも多く含まれているため、血圧降下作用や抗ストレス作用も期待できます。
まとめ
玄米は、白米には少ない食物繊維やビタミンB群、ミネラルなどを豊富に含む栄養価の高い食品です。腸内環境の改善、血糖値の安定、美肌やダイエット、ストレス軽減など多くの健康効果が期待され「スーパーフード」としても注目されています。
「玄米は毒」「健康に悪い」といった噂もありますが、その多くは過剰な不安や誤解に基づいたものです。注意点もありますが、正しく選び適切に食べれば心配はありません。
玄米のメリットとリスクを正しく理解し、自分の体質や生活に合った方法で取り入れることが大切です。むやみに怖がらず、日々の食卓に無理なく玄米を取り入れていきましょう。
この記事を書いた人(執筆者情報)

美容家.com 編集者 – 編集者
本サイトの編集者。美と健康の専門家メディア『美容家ドットコム』の運営、専門家のPR・キャスティング事業を行い、自身も手の専門家として活動。前職であるネイルサロンおよびスクールの経営経験から、女性の年齢が手に現れることに着目し、日本初の手のアンチエイジングに特化した日本ハンドビューティー協会を設立。情報があふれる今、専門家の信憑性の高い情報の必要性を感じ、美容家ドットコムの立ち上げに至る。
株式会社エイジングケア 代表取締役
一般社団法人日本ハンドビューティー協会代表理事
この記事を監修した人(監修者情報)

美容家ドットコム編集部 – 監修者
美容家ドットコムは、美容と健康の各分野における専門家600名以上が登録するプラットフォームです。皆様の疑問に答え、信頼性の高い情報を提供することを目指しています。
本記事は、美容家ドットコム編集部が専門家と協力し、内容を精査・監修のうえ執筆されています。