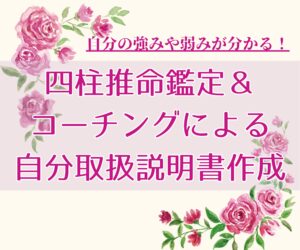バナナは1日何本まで?食べ過ぎた時のデメリットや効果的な食べ方を紹介
朝食やおやつに手軽に食べられるバナナは、多くの人にとって身近な果物ですよね。その栄養価の高さから、スポーツ選手や健康志向の方々にも愛されています。世界的に有名な大谷翔平選手や芸能人もバナナを摂取することを欠かさない人が多く「バナナLoves」という言葉も話題となりました。
しかし「バナナは体に良い」と聞く一方「1日に何本までなら食べても大丈夫?」「食べ過ぎると太るって本当?」といった疑問を抱く人もいるのではないでしょうか。
この記事では、管理栄養士の視点から、バナナを1日に何本まで食べられるのか、また、バナナの栄養素や健康へのメリット、そして気になる「食べ過ぎ」による影響について、わかりやすく解説していきます。
バナナをあなたの食生活に上手に取り入れ、健康的な毎日を送るためのヒントを見つけていきましょう。
バナナってどんな果物?知っておきたいバナナの基礎知識を解説
バナナは手軽でおいしく、栄養も豊富な人気の果物です。実は、バナナにはエネルギー源となる糖質や、カリウム・ビタミン類など、体にうれしい栄養素がぎゅっと詰まっています。この章では、バナナに含まれるカロリーや栄養成分、そして最新版の食品成分表までわかりやすく解説します。
バナナ1本当たりに含まれるカロリー
バナナのカロリーは、その大きさや熟度によって異なります。一般的な大きさのバナナは、可食部約100g1本あたり約86kcalです。これはご飯茶碗半分弱、食パン6枚切り1枚の約半分程度のカロリーに相当します。
【他の果物と比較】
| りんご | 100gあたり約56kcal |
| 柿 | 100gあたり約63kcal |
| ぶどう | 100gあたり約59kcal |
他の果物と比較すると、カロリーは、そこまで大差はありません。バナナは、手軽にエネルギーを補給できる食品として、非常に効率的でしょう。
バナナに含まれる主な栄養素|炭水化物・ビタミン類・ミネラル類
バナナは、私たちの体に必要な様々な栄養素をバランス良く含んでいます。特に注目したい栄養素を3つにまとめご紹介します。
炭水化物
バナナの主成分であり、ブドウ糖、果糖、ショ糖といった糖質が豊富に含まれています。ブドウ糖は体や脳のエネルギー源であり、果糖は甘味の強い果物由来の糖、ショ糖はブドウ糖と果糖が結合した砂糖のことです。
これらは消化吸収が早く、速やかにエネルギー源となるため、運動前や集中したい時のエネルギー補給に最適です。
ビタミン類
バナナに含まれるビタミンB群は、 エネルギー代謝を助けるビタミンB1、B2、B6などが含まれています。特にビタミンB6は、タンパク質や脂質の代謝に関わり、神経機能の維持にも重要な役割を果たします。
また、胎児の正常な発育に不可欠な栄養素である葉酸も含まれており、妊婦さんや栄養素を十分に摂取する必要のある授乳時期にもにおすすめです。さらに、水に溶けやすいビタミンのひとつであるナイアシンは、お肌や粘膜を健やかに保つ働きがあります。
ミネラル類
バナナには、カリウムが含まれ、体内のナトリウム(塩分)を排出し、むくみの解消や血圧の調整に役立ちます。また、マグネシウムも骨や歯の形成、神経機能の維持、筋肉の収縮など、多くの生体反応に関与しています。
バナナと言えば食物繊維が含まれることは有名ですが、整腸作用があり、便秘の改善に役立つ水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の両方を含んでいます。水溶性食物繊維は水に溶けて腸内環境を整え、不溶性食物繊維は溶けずに腸を刺激して働きを活発にする働きがあります。
新しくなったバナナの食品成分表について
日本食品標準成分表は、食品の栄養成分に関する最新の情報を提供するもので、数年ごとに改訂されています。バナナについても、品種や分析方法の進化に伴い、含有される栄養素の数値が更新されることがあります。
たとえば、最新の「日本食品標準成分表2023年版(八訂)」では、一部の成分で過去の版と数値が異なっている場合があります。これは、より正確な情報を消費者に提供するためのものであり、私たちが食品を選ぶ際の重要な根拠となります。
常に最新の情報を参照し、バランスの取れた食生活を心がけることが大切です。
バナナを摂取することで得られる6つのメリットとうれしい効果について

バナナのうれしい美容と健康効果を6つ紹介します。どれもすぐにでも取り入れたくなるポイントです。家族の健康管理や、自分の美容・体調管理のヒントとして、ぜひチェックしてみてくださいね。
脳のエネルギー補給ができて集中力アップ
バナナに含まれるブドウ糖や果糖は、素早く吸収されて脳のエネルギー源となります。脳は主に糖質をエネルギー源として利用しているため、バナナを摂取することで速やかにエネルギーが補給され、集中力や思考力の向上に繋がります。
バナナに含まれる食物繊維で肌荒れが改善
バナナには、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維がバランス良く含まれています。これらの食物繊維は、腸内環境を整え、便通を促進する効果があります。腸内環境が改善されると、老廃物が排出されやすくなり、肌荒れの改善にも繋がります。
また、腸内環境は免疫力とも密接に関わっており、健康的な肌を保つ上で非常に重要です。美容を意識している方にはおすすめのおやつとなりますね。
脂肪燃焼を助けてダイエットをサポート
バナナに含まれるビタミンB群、特にビタミンB1とB2は、糖質や脂質の代謝を助ける働きがあります。これにより、体内で効率的にエネルギーが消費され、脂肪の蓄積を抑える効果が期待できます。
また、カリウムによるむくみ解消効果や、食物繊維による満腹感の持続も、間食を減らすきっかけとなりダイエットをサポートする上で役立ちます。
妊娠・授乳中の栄養補給におすすめ
バナナは、妊娠・授乳中の女性にとって理想的な栄養補給源です。葉酸が豊富に含まれているため、胎児の脳や脊髄のもととなる神経管がうまく閉じなくなる神経管閉鎖障害のリスク低減に効果的です。
また、つわりで食欲がない時でも比較的食べやすく、カリウムやマグネシウムといったミネラルも摂取できるため、電解質バランスの維持や便秘解消にも役立ちます。
赤ちゃんの離乳食にも最適
バナナは、離乳食初期から与えることができる安全で栄養価の高い果物です。歯が生えそろえていない乳幼児も舌で潰すことができるほど柔らかいのが特徴です。
また、消化がよく、赤ちゃんの初めての果物としておすすめです。ブレンダーでペースト状にしたり、小さくカットしたりと、赤ちゃんの成長段階に合わせて調理しやすいのも魅力ですね。
血糖値コントロールに役立つ
バナナには糖質が含まれていますが、食物繊維も同時に摂取できるため、血糖値の急激な上昇を緩やかにする効果が期待できます。
特に、熟度が低いバナナほどレジスタントスターチという消化されにくいタイプのデンプンが多く含まれており、これが血糖値の上昇をさらに抑える働きをします。ただし、熟度が高いバナナは糖度が高くなるため、摂取量には注意が必要です。
バナナを食べ過ぎるとどうなる?食べ過ぎで起こるデメリットを徹底解説

ここでは、バナナの食べ過ぎのデメリットやリスクを6つ紹介します。「体に良い」とされるバナナも、食べ過ぎるとかえって健康を損なう可能性があります。ここでは、バナナの過剰摂取が引き起こす可能性のあるデメリットについて詳しく見ていきましょう。
栄養バランスが偏りやすくなる
バナナばかりを大量に摂取していると、特定の栄養素に偏り、他の重要な栄養素が不足する可能性があります。たとえば、バナナには脂質や鉄などはあまり多く含まれていません。
脂質や鉄が不足すると、体に十分なエネルギーが行き渡らず、疲れやすくなったり、めまいや立ちくらみが起きやすくなり、様々な体の不調に繋がる恐れがあります。
高カロリーとなり肥満の原因になる
バナナ1本あたりのカロリーは決して高くありませんが、何本も食べ過ぎるとその分、総カロリーが高くなります。たとえば、中サイズのバナナを1日3本食べると約258kcal、5本食べると約430kcalにもなります。
これはご飯一杯分以上のカロリーに相当し、消費カロリーを摂取カロリーが上回れば、必然的に体重増加や肥満に繋がるため注意が必要です。
血中の中性脂肪が増える恐れがある
バナナに豊富に含まれる糖質は、エネルギーとして消費されなかった場合、中性脂肪として体内に蓄積される可能性があります。
特に、果糖は肝臓で代謝される際に中性脂肪に変わりやすいという特徴があります。過剰な糖質摂取は、動脈硬化を引き起こしやすくなる高脂血症や肝臓の炎症または機能低下を招く脂肪肝のリスクを高める原因となるため、注意が必要です。
腎結石・尿路結石になるリスクが高まる
バナナには、シュウ酸という成分が含まれています。シュウ酸は体内でカルシウムと結合してシュウ酸カルシウム結晶を形成し、腎臓や尿路に結石ができるリスクを高める可能性があります。
特に、過去に結石を患ったことがある方や、結石ができやすい体質の方は、バナナの過剰摂取を控えるべきです。
胃や腸が消化不良に陥る可能性がある
バナナに含まれる食物繊維は、適量であれば腸内環境を整えますが、過剰に摂取すると消化不良を引き起こすことがあります。
特に、不溶性食物繊維の摂りすぎは、便秘の悪化や腹部の膨満感、ガス溜まりの原因となることがあります。また、熟度の低いバナナに含まれるレジスタントスターチも、人によっては消化器症状を引き起こすことがあるので注意が必要です。
糖質過多で太りやすくなる
前述の通り、バナナは糖質が豊富な果物です。いくら「体に良い」と言えども、糖質を過剰に摂取すれば、インスリンの分泌が促進され、脂肪が蓄積されやすくなります。
特に、運動量が少ない方が大量にバナナを摂取すると、消費しきれない糖質が体脂肪として蓄積され、結果的に太りやすくなってしまうでしょう。
また、バナナによるアレルギーは、成人を中心に世界的に増加傾向にあるというデータもあります。一方で、日本国内ではそのような報告は比較的少ないとされています。
しかし、体質によってはバナナを多く摂取することでアレルギー反応を引き起こす可能性もあるため、1日1本程度を目安に、適量を心がけて摂取するようにしましょう。
バナナを1日3本は食べ過ぎ?1日の適量と毎日食べ続けた場合の効果について
「バナナは何本までなら健康にいいのか?太るのか?」と気にする声が聞かれます。ここでは1日に摂取する適量の目安とその根拠を解説します。
バナナの1日の目安本数
健康な成人が1日に摂取するバナナの適量は、一般的に1〜2本が目安とされています。これは、日本人の平均的な食生活を踏まえ、果物から摂る糖質の量や、ビタミン・ミネラルとのバランスを考慮したうえで導き出されたものです。
バナナは栄養豊富である一方、糖質も含んでいるため、「体にいいから」といって食べすぎると、かえって栄養の偏りを招く可能性もあります。
バナナ1本~2本が適量な理由|糖質過多の防止・栄養バランスの維持・カリウム摂りすぎの回避
バナナを1~2本に抑えることには、以下のような複数のメリットがあります。
糖質過多の防止
1~2本であれば、一日の総糖質摂取量を適正範囲に抑えやすく、血糖値の急激な上昇や中性脂肪の増加を防ぐことができます。
栄養バランスの維持
バナナに限らず、さまざまな食品から栄養を取り入れることで、食事全体のバランスが整いやすくなります。ひとつの食材に偏った食生活を続けていると、どれだけ健康に良いとされている食品でも、かえって特定の栄養が不足したり、逆に過剰になる恐れもあるのです。
日々の食事は、バランスの積み重ねです。いろいろな食材を組み合わせて食べることが、健やかな体を育む土台になりますね。
カリウム摂りすぎの回避
バナナはカリウムが豊富ですが、腎機能が低下している人がカリウムを過剰に摂取すると、高カリウム血症を引き起こす可能性があります。健康な人であっても、適量を守ることで安心して摂取できます。
このように、毎日バナナを1~2本食べ続けることは、腸内環境の改善、便秘の解消、血圧の安定、集中力の維持など、長期的な健康維持に貢献するでしょう。
バナナの食べ過ぎで死亡?食べない方がいい人の特徴を紹介
バナナを食べ過ぎたことによる直接的な死亡のリスクは、健康な人であれば極めて低いと言えます。
しかし、特定の疾患を持つ人にとっては、過剰なバナナの摂取が健康上の問題を引き起こす可能性があります。
特に注意が必要なのは、腎機能が著しく低下している方です。腎臓は体内のカリウム濃度を調整する重要な役割を担っていますが、腎機能が低下するとカリウムを適切に排出できなくなり、血中のカリウム濃度が異常に高くなる高カリウム血症を引き起こす可能性があります。
高カリウム血症は、不整脈や心停止など、命に関わる重篤な症状を引き起こす恐れがあるため、腎臓病の患者さんはバナナを含むカリウムの多い食品の摂取量について、主治医や管理栄養士に相談するようにしましょう。
また、糖尿病を患う人も、バナナの糖質が血糖値に影響を与えるため、摂取量には注意が必要です。血糖コントロールの状態に応じて、適量を守り、食後の血糖値の変化を確認しながら摂取することが大切です。
健康な人であれば、常識的な範囲でのバナナの摂取は安全であり、むしろ健康に寄与するメリットの方が大きいといえます。
なお、赤ちゃんや幼児にバナナを与える場合も、1日1/2~1本程度が適量です。柔らかく消化もしやすい反面、糖質量が多い点には注意が必要です。
バナナがダイエットに向いている理由や太りにくい摂取タイミングを解説
バナナを食べてダイエットしたい人向けにおすすめの食べ方を紹介します。
バナナがダイエットに向いている理由|低カロリー・むくみ対策・代謝をサポート
バナナは、その栄養特性からダイエットの強い味方です。ここでは、バナナがダイエットに向いている理由と、効果的な摂取タイミングについて4つ解説します。
比較的低カロリー
他の甘いお菓子や加工食品に比べて、バナナは満足感を得やすい割にカロリーが控えめです。間食をバナナに置き換えることで、総摂取カロリーを抑えることができます。
むくみ対策
豊富なカリウムが、体内の余分なナトリウム(塩分)を排出するのを助け、むくみの解消に繋がります。むくみが解消されると、見た目もすっきりし、ダイエットのモチベーション維持にも役立ちます。
代謝をサポート
ビタミンB群が糖質や脂質の代謝を円滑にし、効率的なエネルギー消費を促進します。これにより、脂肪が燃焼しやすい体作りをサポートしてくれます。
食物繊維による満腹感と便秘解消
食物繊維が消化を緩やかにし、満腹感を長く持続させます。また、腸内環境を整えて便通を改善することで、体内の老廃物排出を促し、ダイエット中の不快な症状を和らげます。
バナナのおすすめ摂取タイミング|朝・昼・夜
バナナをダイエットに効果的に取り入れるには、摂取タイミングも重要です。ここでは、摂取のタイミングを4つ紹介します。
朝
朝食にバナナを食べることで、午前中の脳のエネルギー源を素早く補給し、集中力を高めることができます。また、朝食を抜くことによる反動の食べ過ぎを防ぎ、規則正しい食生活を送る手助けになります。
また、他の食品と組み合わせることで、栄養バランスも整えやすくなります。
たとえば、バナナとプロテインを組みわせることで、スムージーを作る際も簡単に調理ができおすすめです。
昼(食前や食間)
昼食の前にバナナを少量食べることで、血糖値の急上昇を緩やかにし、食べ過ぎを抑制する効果が期待できます。また、午後の小腹が空いた時のおやつとして取り入れることで、高カロリーなお菓子への欲求を抑えることができます。
ちなみに基本的にバナナは、3~4房で、100円~200円代で購入することができます。おやつとして安く購入できるのもお財布に優しいおやつですね。
運動前・運動後
- 運動前: 運動の30分~1時間前にバナナを摂取することで、即効性のエネルギー源となり、パフォーマンスの向上に役立ちます。
- 運動後: 運動後の筋肉の回復に必要な糖質を素早く補給し、グリコーゲンの再合成を助けます。また、カリウムは発汗によって失われたミネラルを補給するのにも適しています。
夜
夜のバナナ摂取は、寝る直前でなければ問題ありませんが、消化に時間がかかるため、就寝の2~3時間前までには済ませるのがおすすめです。夜食として食べる場合は、少量に留め、寝る前の血糖値の急上昇に注意しましょう。
まとめ
バナナは、手軽にエネルギーと多様な栄養素を補給できる、私たちの食生活にとって非常に有益な果物です。豊富な炭水化物が脳の活性化を促し、食物繊維が腸内環境を整え、カリウムがむくみ解消に貢献するなど、様々な健康効果が期待できます。
しかし、「体に良いから」といって無制限に食べるのは禁物です。1日に1~2本を目安にすることで、糖質の過剰摂取を防ぎ、他の食品からの栄養素もバランス良く取り入れ、偏りのない食生活を送ることができます。
特に、腎臓病の方や糖尿病の方は、摂取量について専門家のアドバイスを仰ぐことが重要です。
バナナを賢く食生活に取り入れ、あなたの健康的な毎日をサポートしていきましょう。
この記事を書いた人(執筆者情報)

平岡 伊都栄 – 管理栄養士
管理栄養士としての専門知識と実務経験を活かし、体質やライフスタイルに合わせた食に関する執筆を中心にライターとして活動している。
幼少期にアトピー性皮膚炎を患った経験から、食べるものが体に与える影響を実感。当時、母が用意してくれた有機野菜中心の手料理が、少しずつ肌や体調を整えてくれたことが「食の道」への原点となる。大学卒業後は食品添加物の検査員として勤務し、食品の安全性に関わる仕事に従事。大学で学生や保護者向けの弁当提案やアレルギー対応などを経験。
この記事を監修した人(監修者情報)

美容家ドットコム編集部 – 監修者
美容家ドットコムは、美容と健康の各分野における専門家600名以上が登録するプラットフォームです。皆様の疑問に答え、信頼性の高い情報を提供することを目指しています。
本記事は、美容家ドットコム編集部が専門家と協力し、内容を精査・監修のうえ執筆されています。