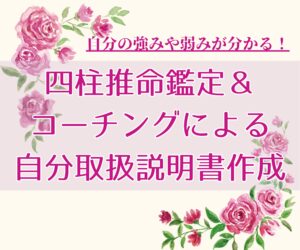たくあんの食べ過ぎで太る?気持ち悪い時や腹痛の対処法、一日の摂取量を解説
たくあんを食べた後や翌日に、顔のむくみや胃腸の不調に悩まされて「食べ過ぎたかも…」と後悔したことがありませんか。
たくあんには、健康・美容・ダイエットに嬉しい効果がたくさんありますが、大切なのは「適量を、上手に取り入れる」ことです。
この記事では、たくあんの魅力と健康効果、そして食べすぎた時の対処方法まで分かりやすく解説します。
ついつい食べ過ぎてしまう「たくあん」その魅力とは?
たくあんの具体的な栄養情報を知ることで、たくあんをもっと上手に楽しむことができるかもしれません。たくあんに含まれる栄養素と健康効果について解説します。
たくあんに含まれる栄養素と健康効果

たくあんの素材は大根なのでヘルシーなイメージがありますよね。たくあんにはどのような栄養素が含まれているのでしょうか。同じ大根を使ったべったら漬けの栄養価を比較しました。べったら漬けとは塩漬けした大根を米麹と砂糖で漬けた漬物のことです。
| たくあん漬け (100gあたり) |
べったら漬け (100gあたり) |
食事摂取基準(2025年版) | |
| エネルギー (kcal) | 21kcal | 53kcal | 1750kcal |
| たんぱく質 (g) | 1.9 g | 0.4g | 50g |
| 食物繊維 (g) | 3.7g | 1.6g | 18g |
| カリウム (㎎) | 500mg | 190mg | 2,000mg |
| ビタミンB1(㎎) | 0.21mg | Tr | 1.1mg |
| ビタミンC (㎎) | 12mg | 49mg | 100mg |
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」参照
※女性30歳~49歳の女性 身体活動レベル低いの基準を使用
※食品は100gあたりの栄養価
たくあん漬けとべったら漬けを比較すると食物繊維やカリウム、ビタミンB1において、いずれもたくあん漬けの方が栄養価が高いことがわかります。
理由は大根を干すことで水分が抜けるため栄養素が凝縮されるためです。栄養価が増える以外にも大根を干すことで、うま味成分であるアミノ酸やグルタミン酸も増えることがわかっています。
また、たくあんの方が低カロリーなのも嬉しいポイントですね。
次に、たくあんに含まれる栄養素と効能を解説します。
乳酸菌
たくあんには乳酸菌が含まれており腸の中の善玉菌を増やすとともに悪玉菌の繁殖を抑え、腸内環境を整えることが期待できます。
全身の免疫細胞のうち60〜70%が腸にあると言われていますが、腸内の善玉菌が増えると免疫力が活性化し、風邪やウィルス性の病気になりにくくなりアレルギー症状の予防や緩和にも繋がります。
また、たくあんに含まれる乳酸菌は食物性乳酸菌で、胃酸に強いという特性があります。ヨーグルトなどに含まれる動物性乳酸菌よりも胃での生存率が高く、腸管にまで到達する可能性が高いと言われています。
食物繊維
食物繊維は便秘の改善や腸内環境を改善に効果的です。さらに、コレステロール値の低下や高血圧の予防など、生活習慣病対策としての効果が期待できます。食物繊維は腸内の善玉菌のエサとなって、その働きをサポートする役割もあります。
前項で解説した乳酸菌や納豆菌など、腸によい影響を与える菌そのものを「プロバイオティクス」と言い、食物繊維のように腸内の善玉菌のエサになる食品を「プレバイオティクス」と言います。また「プロバイオティクス」と「プレバイオティクス」を一緒に摂ることを「シンバイオティクス」と呼び、相乗効果で腸内環境改善に効果的と最近注目されています。
ビタミンB1
糖質の代謝に関わり、糖質をエネルギーに変える働きがあります。ご飯と一緒に食べることで効率よく糖質をエネルギーに変換できます。また疲労物質の乳酸の蓄積を防ぎ疲労回復をサポートします。
ビタミンC
抗酸化作用がありコラーゲンの合成を助けシミやシワを防ぎます。免疫力を高める働きが強く、風邪などのウィルス性の病気から守ってくれます。また、ビタミンCは抗ストレスビタミンとも言われており、免疫機能の向上や疲労回復、目の疲れ予防効果も期待されています。
カリウム
体内の余分な水分やナトリウムを体外に排出し血圧を下げる効果があります。
GABA(γ―アミノ酪酸)
たくあんにはGABAという神経伝達物質が多く含まれています。GABAには神経の興奮をしずめる抗ストレス作用があると言われれいます。たくあんには、発芽玄米の約10倍ものGABAが含まれています。
GABAの主な効果
- イライラをやわらげる
- 精神をリラックスさせる
- 血圧降下作用
- 睡眠の質を向上
たくあんには栄養が豊富に含まれており、健康に嬉しい効果が期待できますね。
たくあんが与える美容に対する効果
たくあんには強い抗酸化作用のあるビタミンCが含まれており、肌のシミやくすみ、老化予防に役立つとされています。また、肌のターンオーバーを促しコラーゲンの生成を促進し、肌のハリや弾力を高めます。
たくあんに含まれる乳酸菌や食物繊維は腸内環境を整えることで免疫力を高めてくれて、老化にともなう病気や炎症を軽減しアンチエイジング効果が期待されます。腸内環境が整うと、栄養素の吸収効果も高まり、代謝が促進され老廃物が排出されるため、肌や体調が整いやすくなります。
たくあんを食べ過ぎたらどうなる?高血圧やむくみ等の健康リスクを分かりやすく解説
たくあんを食べ過ぎると次のような症状が現れることがあります。
- 血圧の上昇
- 喉の渇き
- むくみ
- 胸やけ
- 腹部不快
体調不良の症状が引き起こされる理由を詳しく見ていきましょう。
たくあんを食べ過ぎて「気持ち悪い」「お腹が痛い」といった体調不良の症状が引き起こされる原因
たくあんを食べ過ぎると体調不良の症状が現れるのは、塩分過多や胃酸の過剰分泌、乳酸菌や食物繊維の摂り過ぎなどが考えられます。
塩分過多
塩分を摂り過ぎると血圧が高くなります。また血液中のナトリウム濃度が上がるため、むくみが生じます。さらに、腎臓や骨にまで影響する可能性があります。
腎臓は塩分を尿として排泄する働きがあり、摂り過ぎると腎臓に負担がかかります。塩分を摂り過ぎるとカルシウムが外へ排出されてしまうため、骨からカルシウムを補充するため骨粗しょう症を引き起こすこともあるのです。
胃酸の過剰分泌
たくあんは食べ過ぎると胃酸の分泌が促進され、食道に胃酸が逆流して胸やけや胃もたれを引き起こすことがあります。
乳酸菌や食物繊維の摂りすぎによる腹痛
たくあんは乳酸菌や食物繊維を含んでいるため、食べ過ぎると下痢や腹痛を起こすことがあります。
たくあんを食べ過ぎた時の対処法

たくあんを食べ過ぎた時は以下の対処法を試してみてください。
水分補給
水分を多く摂り尿量を増やし塩分を排出します。利尿作用があるコーヒーやお茶などが効果的です。
野菜や果物を摂る
カリウムが豊富な食材を摂ると、ナトリウムを体外から排出させるのを促す効果があります。
<カリウムを多く含んでいる食品>
・生野菜 ・生果物 ・イモ類 ・カボチャ ・切り干し大根 ・豆類
運動で汗をかく
有酸素運動や入浴して汗をかくことで体内の塩分を排出する助けになります。
塩分を控えた食事にする
塩分を摂り過ぎたら当日や翌日の食事を調整しましょう。
塩分量の多い食品は控えたり、香辛料や酢、出汁を上手に利用し減塩をしましょう。
上記の対処法でも、不調が改善されない場合は医師に相談しましょう。
理想的な一日の摂取量を紹介
たくあんは一日にどのくらいの量を摂取するのがよいのでしょうか?
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準2025年版」によると、15歳以上の男性の1日の食塩摂取量の目標量は7.5g未満、女性は6.5g未満です。
たくあんの厚さにもよりますが、1切れ8mmでカットすると、ナトリウムは93mg「食塩相当量は0.23g」とされています。ほかの食事からの塩分も考慮して、1日に食べるたくあんの枚数は3枚程度がよいでしょう。
ただし、人によって1日の運動量や汗をかく量、食事全体からの塩分摂取量は異なるため、あくまで目安と考えてください。
塩分や栄養バランスに注意!たくあんを食べる時の注意点について

たくあんを食べるときは、どのようなことに気をつけて食べるとよいでしょうか。
塩分量
たくあんは保存食なので多くの塩分を含んでいます。食べる際には量に注意し、塩分をよく洗い流すと塩分量を減らせます。
添加物
たくあんは本来、天日干しをした大根を塩と米ぬかに漬けて発酵させたもので添加物は入っていません。しかし市販のたくあんは、少なからず添加物が入ってます。購入するときはパッケージ裏の原材料欄をチェックして、添加物が少ない商品を選ぶようにしましょう。
例えば、着色料は天然着色料(クチナシ色素・ウコン色素)を使用しているものがよいでしょう。甘味料は天然由来のステビアや安全性が確認できているスクラロースを使用しているものがおすすめです。
保存方法
たくあんは開封前は賞味期限が長いですが、開封後は冷蔵庫で保管し、早めに食べきりましょう。
栄養バランス
たくあんとご飯だけなど偏った食事ではなく、たんぱく質や他の野菜などを組み合わせて栄養バランスの取れた食事がよいでしょう。
たくあんが与えるダイエットへの効果と注意点
たくあんを食べることでどのような効果と注意点があるのでしょうか。
ダイエットへの効果
たくあんは低カロリーで食物繊維が豊富な発酵食品なので、ダイエットにも取り入れやすい食品です。たくあんは100gあたりのエネルギーは21kcalで低カロリーです。通常一度に食べる量は約25g程度なのでエネルギーは約5kcalでダイエットに向いているといえるでしょう。
さらに、たくあん特有のパリパリ食感は自然と噛む回数が増えるため、少量でも満腹感が得られます。よく噛むことで、食事全体のスピードもゆっくりになり、食べ過ぎの予防にもつながるのが嬉しいポイントです。
また、たくあんには食物繊維が豊富に含まれているため、便秘によるぽっこりお腹が気になる人にはおすすめです。さらに代謝を促すビタミンB群も含まれています。
ダイエットする時の注意点
たくあんは塩分が含まれているので食べ過ぎると水分を溜め込みやすくなります。その結果、むくみやすく体重が一時的に増加することもあります。
たくあんのおすすめの食べ方3選!
たくあんを使った、おすすめレシピを紹介します。
健康志向の人向け:たくあんとチーズの納豆和え
【材料(1人分)】
- たくあん 2切れ
- 納豆 1パック
- カマンベルチーズ 1個
- ネギ 適量
<作り方>
たくあんとチーズは5〜6㎜の各切。材料を混ぜて、納豆のタレを入れて絡ませます。
最後にネギをのせて完成
*ポイント
納豆とたくあん、チーズは発酵食品で乳酸菌と納豆菌の組み合わせで、腸内環境が活性化します。
チーズはカルシウムとたんぱく質が豊富でどちらも骨の構成成分です。
ネギに含まれるアリシンが疲労回復や血行促進に効果があります。
美容が気になる人向け:長芋とたくあんのごまサラダ
【材料(3~4人分)】
- 長芋 150g
- たくあん 4枚
- 大葉 2枚
- すりごま(白) 適量
- 刻みのり 適量
- 米酢 大さじ2
- 砂糖 大さじ1
- 醤油 小さじ1/2
- 出汁 小さじ1
<作り方>
長芋は8㎜の角切りにし酢水(分量外)につける。たくあんも同様に角切りにする。
長芋とたくあんに調味料を入れて混ぜる。すりごまも混ぜて直前に刻みのりをのせる。
*ポイント
長芋はムチンが豊富で、肌や粘膜を保護し、ビタミンCも含まれ美白やコラーゲンの生成にも効果的です。すりごまはビタミンEが豊富で抗酸化作用により、肌の老化を防いでくれてアンチエイジングにピッタリな食材です。刻みのりはミネラルが豊富で肌や髪の健康維持に効果的です。
長芋とたくあんを角切りにして、よく噛むことでフェイスラインの引き締め効果もあります。
ダイエットしたい人向け:切り干し大根とたくあんのゴマポン酢和え
【材料(3~4人分)】
- 切り干し大根 40g
- 胡瓜 1本
- たくあん 5枚
- ポン酢 適量
- ごま油 適量
- いりゴマ 適量
<作り方>
切り干し大根は水で戻し食べやすい長さにカットする。たくあん、胡瓜は千切りにし、胡瓜は軽く塩をふり水切りする。すべてを合わせ、ポン酢、ごま油を適量かけて混ぜ合わせ、最後にごまをかける。
*ポイント
切り干し大根は噛みごたえがあり、満腹感があり食べ過ぎを防いでくれます。ミネラルも豊富で代謝やむくみを防止してくれます。胡瓜は低カロリーでカリウムを含み、余分な水分を排出してくれます。ゴマのセサミンやビタミンEが抗酸化作用を発揮し、老化を防ぎます。
スーパーやお店でたくあんを選ぶ時のポイントは?
スーパーに沢山のたくあんが売られていますが、たくあんの種類は大きく分けると3つに分かれます。それぞれの特徴を説明します。
干したくあん
たくあんを天日干ししてから漬け込む方法です。昭和の初めまでは、ほとんどがこの方法で行われていました。大根を天日干しすることで水分が抜け、栄養素が凝縮します。食物繊維が増加しアミノ酸やグルタミン酸など、うま味成分が増加します。
塩押したくあん
食塩で水分を抜いてから漬け込む方法です。スーパーで購入できるほとんどが塩押したくあんです。
昔ながらの干したくあんに比べ、食物繊維やミネラルは少なめですがビタミンCは干したくあんより多く含まれています。
燻製たくあん
室内で燻してから漬け込む方法です。秋田県の名産、いぶりがっこが有名です。独特の風味や食感が楽しめます。ビタミンやミネラルは干したくあんより少ないですが、食物繊維は干したくあんの2倍含まれています。
たくあんを購入するときは、たくあんの種類や自分の好みにあった、たくあんを選ぶと良いですね。
たくあんへの正しい知識を手に入れて、毎日の食卓をもっと豊かに
たくあんは日本の知恵と食文化が詰まった伝統食品です。
江戸時代から400年経った現在まで食卓のお供として親しまれてきた日本のソウルフードです。
独特の歯ごたえや香りだけでなく、腸内環境を整える乳酸菌や食物繊維を含むことから、ダイエットや美容、健康にも役立ちます。ただし、塩分が多くむくみや高血圧、胃腸の不調などのリスクもあるので、適量を食べることがポイントです。
たくあんはアレンジも自由自在な食材で、納豆、海苔、豆腐などの健康食材と組み合わせると、毎日の食事が楽しく、体に優しいものになります。”適量”を心がけ、魅力いっぱいのたくあんを美味しく、健やかに楽しんでみてくださいね!
この記事を書いた人(執筆者情報)

澤村 葉子 – 管理栄養士
管理栄養士として高齢者施設の栄養サポートに長年従事し、現在は健康情報を発信するライターとして活動しています。人生の最期まで”口から食べる”ことを楽しんでほしい、そんな思いから摂食嚥下認定士として高齢者の栄養管理に力を注いできました。発酵食品マイスターの知識を取得し、腸活や免疫力アップなど、体に優しい暮らしのヒントを発信しています。
この記事を監修した人(監修者情報)

美容家ドットコム編集部 – 監修者
美容家ドットコムは、美容と健康の各分野における専門家600名以上が登録するプラットフォームです。皆様の疑問に答え、信頼性の高い情報を提供することを目指しています。
本記事は、美容家ドットコム編集部が専門家と協力し、内容を精査・監修のうえ執筆されています。